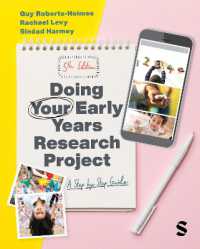出版社内容情報
建築体験とは、その地で食べた屋台飯や雑踏の匂い、喧騒、道行く人のふるまいや耳にした会話と不可分だ。31年間で54の国と地域を巡り、「生きた時空間」の中で建築と出会いつづける著者による旅の記録術。3000頁超のノートづくりに裏打ちされた図法選択や聞取り・実測手法、速記や時短着彩のテクニック、人や食の描き方。
【目次】
巻頭グラビア(18頁分)
はじめに:旅で学ぶ建築、体験を刻むノート
第1章 フィールドノートのはじめかた
1|なにを採集するのか?
・気になったらなんでも描く
・体中のアンテナで瞬間の世界を取り込む
・どんな天気でだれと言葉を交わしたか
2|道具と基本の描き方
・お気に入りの道具を揃える
・道具の選択
・手順のダイジェスト
・予測不可能な旅をまるごと記録する
3|その場で書く、その日のうちに描く
・インタラクティブな対話
・イラストは現場で描きあげる
・書き文字はメモ帳経由で!
4|なにを描くか、どう描くか?
・描くもの、描かないものを取捨選択する
・まず絵を描き、文字は隙間に流す
5|描く以外にも、採集する
・10年後も残る臨場感
・小さく薄いホンモノを集める
・人の声を集めてまちを見る
━travelog①
旅の出会いを筆跡で残す:ボスニア・ヘルツェゴビナ、中国、カザフスタン、台湾
━travelog②
言語が変わればレイアウトも変わる:台湾
第2章 旅の描き方 ・歩き方
1|出発:行きのフライト
・デイバックとウエストポーチ
・チケットとバゲージ用シール
・機内でノートを広げたら
・見返しにつくる指さし会話集
2|到着:まず大きく歩く
・目的地もルートも決めずに
・バザールでは立ち止まる
・自分の変化を相対化する
・右に曲がるか、左に曲がるか
3|クローズアップ調査?観察する
・ためらわず座り込む
・描くから気づくこと
・興味がなくても記録する
・観劇で異国の日常をあぶりだす
━travelog③
異国の非日常から日常を知る:シリア、台湾
4|休憩と食
・食事は旅の最大の快楽
・熱いうちに食べよ!
━travelog④
食は文化と社会を表す:キルギス
5|移動:車窓と車内を記憶する
・描きたい景色を選び取る
・寝台車を測る
・長距離列車で友だちをつくる
・バスが止まるとペンをとる
・1日を見開き紙面に収める
・振り返ると面白い、おこづかい帳
6|宿での時間整理する作業
・ホテルの部屋を実測する
・メモから地図 ・文字を起こす作業
・忙しい旅の夜はドライヤー
・会議や講演会を記録する
・図面はきれいに仕上げたい
・間取図のプロセス:方眼なし編
7|帰国:機内の編集作業
・駆け込み仕上げ&貼りモノ作業
・旅の終わりのカタルシス。目次づくり
・次の旅への伝言
8|乗継:疾駆するスケッチマラソン
・最小限の線で描く
目次
はじめに 旅で学ぶ建築、体験を刻むノート
第1章 フィールドノートのはじめかた
第2章 旅の描き方・歩き方
第3章 建築を刻む図法と実測術
第4章 ぐっと情報量が増す!編集テクニック
おわりに フィールドワーカーとして生きる
著者等紹介
渡邉義孝[ワタナベヨシタカ]
1966年生まれ。一級建築士、風組・渡邉設計室代表。尾道市立大学非常勤講師。尾道空き家再生プロジェクト副代表理事として空き家再生・空き家バンク事業を担当。住宅設計、民家再生、文化財調査等の業務のかたわら、主にユーラシア各地の伝統的建築のフィールドワークを続け、訪問国は54ヶ国・地域。2011年に東アジア日式住宅研究会メンバーとして台湾に渡り、以降35回渡航。2019年から台南市観光顧問を務め、台湾ユニット老屋顔とともに講演も行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 電子書籍
- 私が愛した人は優しい悪魔でした【タテヨ…