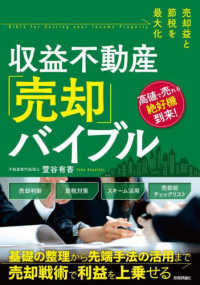出版社内容情報
代議制民主主義の限界が露呈するなか、無作為抽出による少人数グループが十分な専門的情報を得て熟議を行い、提言を策定して公共政策の検討過程へ反映させるミニ・パブリックスと呼ばれる取組みが拡大している。世界289事例の分析をふまえ、成功のための原則、既存の制度に熟議を埋め込む方法をまとめた初の活用ガイドライン。
内容説明
代議制民主主義の限界が露呈するなか、無作為抽出による少人数グループが十分な専門的情報を得て熟議を行い、提言を策定して公共政策の検討過程へ反映させるミニ・パブリックスと呼ばれる取組みが拡大している。世界289事例の分析をふまえ、成功のための原則、既存の制度に熟議を埋め込む方法をまとめた初の活用ガイドライン。
目次
1 熟議とガバナンスの新しい姿
2 熟議プロセスの様々なモデル
3 熟議プロセスをめぐる世界のトレンド
4 成功する熟議プロセスとは?―エビデンスから考える
5 公共的意思決定のための熟議プロセス成功の原則
6 民主主義を再構築する―なぜ、どのように熟議を埋め込むか
7 その他の注目すべき熟議の実践
8 結論
1 ~ 1件/全1件
- 評価