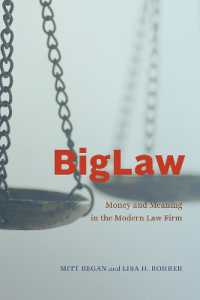出版社内容情報
認知症・鬱病・運動不足による各種疾患…。医療をめぐるさまざまな問題の最上流には近年深まる「社会的孤立」がある。従来の医療の枠組みでは対処が難しい問題に対し、薬ではなく「地域での人のつながり」を処方する「社会的処方」。制度として導入したイギリスの事例と、日本各地で始まったしくみづくりの取り組みを紹介。
目次
はじめに
はじまりは一人の婦人からだった
1章 目に見えない「孤立」という病
地域とのつながりが未来を照らす
つながりがないことは寿命を縮める
日本において本当に社会的孤立は存在するのか?
イギリスにおける社会的孤立と「孤独担当大臣」
イギリスの社会的処方
イギリスの社会的処方の例 言葉ではなくアートで対話する「drawing life」
社会的処方は人を「健康」にすることを目的にするのではない
マイナスをプラスにするのではなくプラスをダブルプラスへ!
2章 社会的処方のカナメ リンクワーカー
「暮らしの保健室」ができるまで
暮らしの保健室は「対話を通じて自らを取り戻す場所」
リンクワーカーとはつながりを作る人
例えばこんなリンクワーカー:ブロムリー・バイ・ボウセンター
ABCD:どんな人でも地域を良くする力を持っている!
リンクワーカーの育て方:BBBCの場合
日本では「みんながリンクワーカー」にしようよ
制度にするのか、文化にするのか
「みんながリンクワーカー」になることで、あなたも楽になる
私たちが考える「リンクワーカーらしさ」とそのスキル
日本のリンクワーカー:コミュニティユースワーカー
3章 社会的処方を市民の手で
市民による意思決定支援 Lay navigatorとCo-Minkan
公民館とCo-Minkan
社会的処方研究所
社会的処方研究所を大きく変えた「アカギさんの事例」
孤独を愛する人は、つなげる必要はない?
4章 まちに医療者が関わる 日本で広がる社会的処方①
医師が屋台をひいて、コーヒーを配る
医療で人は呼べないという原体験
「医療者である○○さん」から「モバイル屋台の○○さんは医療者だった」に
巻き込むことで、その人らしさを内包する
巻き込まれることで、気づいたら健康になる街へ
小規模多機能なモバイル屋台の役割
食べることを通じて孤立を防ぐ 「みんなで食べる」が生きるを支える
タバコはやめられるか?愛煙家座談会と愛煙家登山
禁煙するつもりなし!
愛煙家で集まろう
愛煙家で山に登ろう
愛煙家で主張しよう
何が人を動かすのか
5章 暮らしを彩る年の差フレンズ 日本で広がる社会的処方②
高齢者と学生が一つ屋根の下で暮らす次世代下宿「京都ソリデール」
まちに帰属する「書生生活」
高齢者住宅のあらたな取り組み 「仕事付き高齢者住宅とは」
全国に広がる「ごちゃまぜ」の社会
6章 リンクワーカーからみた社会的処方のタネ
「本」を媒介にして人がつながっていく こすぎナイトキャンパス
「かってにやると、おもしろくなる」 連鎖するまちの文化
身体を流れる音楽 福祉施設×劇場「アーティストとともに過ごす時間」
アートの世界に広がる社会的包摂(social inclusion)
アートの力で高校中退者を減らす
劇場からもっとも遠い人たちに、アートを届ける
「進化系スナック?」 対話式カレー屋の目指す未来
こども食堂と丸亀市「ばば食堂あんもち部屋」
ばば食堂に「帰る」子どもたち
おわりに 「はじまりの婦人」にもう一度会えたら
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
山口透析鉄
うさうさ
kitten
joyjoy
-

- 電子書籍
- 金運大全(大和出版) - 仕事運、財運…