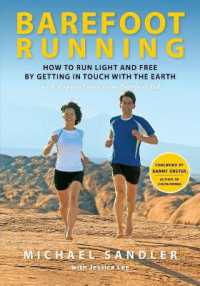内容説明
日本にもやってきたMaaSブーム。だが日本では自動車業界の新規ビジネスのネタとして紹介されることが多い。本書は、世界と日本の動きをもとに、各種の公共交通の利便性向上で脱マイカー依存を実現し、都市と地方を持続可能にする強力な政策ツールとしてのMaaSの活かし方を徹底解説。交通・ICT・地方創生関係者、必読の1冊。
目次
序章 MaaSは交通まちづくりの最強ツール
第1章 フィンランドから世界に広がるMaaS
第2章 MaaSの源流になったスマートテクノロジー
第3章 フィンランドとヘルシンキの政策
第4章 MaaSが生まれた理由
第5章 ヘルシンキでMaaSを体感する
第6章 世界で導入が進むMaaS
第7章 自動車メーカーがMaaSに参入する理由
第8章 ルーラル地域とMaaS
第9章 日本でのMaaSの取り組み
第10章 日本でMaaSを根付かせるために
著者等紹介
森口将之[モリグチマサユキ]
1962年東京都生まれ。早稲田大学卒業後、出版社編集部を経て1993年にフリーランスジャーナリストとして独立。国内外の交通事情・都市事情を取材し、雑誌・テレビ、ラジオ・インターネット・講演などで発表。2011年には株式会社モビリシティを設立し、モビリティやまちづくりの問題解決のためのリサーチ、コンサルティングを担当する。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員、グッドデザイン賞審査委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新空调硬座普快卧
3
MaaS本の中で最もしっくりくる本。MaaS事例紹介も良いが、その前後のMaaSに対する考え方に同感。日本にあふれているのは”あやかりMaaS”で、BRTの二の轍を踏むなと。拡大解釈で本質をぼやかし、利用者からメリットが見えにくい仕組みに引きずり下ろすのをやめようということ。そのうえで、地の公共交通自体の一体化改革が重要だと。2019/10/24
k
1
勉強になった。2024/03/17
池谷真由
1
仕事のために読みました。知っているようで知らなかったことがたくさんあって、勉強になりました。ビジネス書は嫌いだと思ってたけど、意外と楽しく読めた。
kurikuri
1
まずは、MaaSの誤解を解くところから始まる。MaaSは一つの手段であり、そこを目指すのではない。事業者都合で考えるのではなく、顧客の為には何が必要かを考える。そして、地方型と都市型のMaaSを論議しているが、こと地方にで、その都市毎の課題が異なることを理解した。他の地方のことを、コピーするだけではいけない。日本は交通を民間企業が管理し、赤字黒字で路線を増やしたり減らしたりするが、それは顧客のことを本当に考えたものなのか、問われている。日本におけるMaaSの導入には、地方自治体の力も必要だと考えられる。2020/09/24
てぃげる
1
Maasについての教科書的な本 特に印象に残ったのはMaasは商業的なものではなく、環境や交通の革命のためであるというところであった。 ここから、さらに具体的な事案や本に向かうべきだと思った。2020/09/04
-
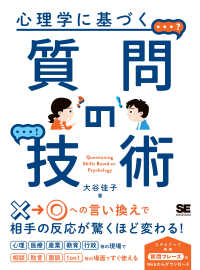
- 和書
- 心理学に基づく質問の技術
-
![別冊フレンド2016年3月号[2016年2月13日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0307383.jpg)
- 電子書籍
- 別冊フレンド2016年3月号[2016…