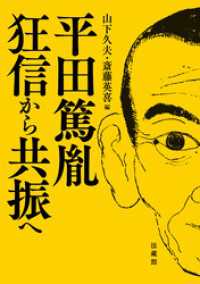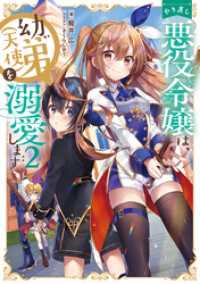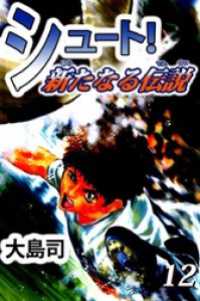内容説明
被災県で陣頭指揮し、様々な問題に直面した著者が、混乱の中で行われた建設の真実と、今後の震災への教訓を語る。
目次
序章 仮設住宅とは
1章 被災直後から仮設住宅建設初期の対応まで―現場から
2章 仮設住宅の完成・避難所の閉鎖まで―俯瞰して見てみる
3章 東日本大震災における仮設住宅の達成点と問題点
4章 得られた教訓と将来への展望
終章 災害救助法について思う
著者等紹介
大水敏弘[オオミズトシヒロ]
1970年生まれ。大槌町副町長。技術士(建設部門(都市及び地方計画))。1993年東京大学工学部建築学科卒業後、建設省(現国土交通省)入省。関東地方整備局建政部住宅整備課長、岩手県県土整備部建築住宅課総括課長、国土交通省都市局市街地整備課企画専門官等を歴任。地域振興整備公団在任時に、沖縄市や防府市の市街地再開発事業に携わり、その後水戸市都市計画部長として都市整備を担当するなど、地方都市の市街地整備に長く関わっている。東日本大震災時には、岩手県庁に勤務しており、以降1年間、災害対策の最前線で仮設住宅建設等の業務に当たる。平成24年度の1年間は国土交通省本省で復興事業の担当官となり、平成25年4月から現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
8
新刊棚。「応急仮設住宅」が正式名(9頁)。阪神・淡路大震災の資料は役立ったという(25頁)。教訓を活かして前進していく勇気。被災規模の大きい地域からの着工(28頁)。整備の4原則:①地域一括②被災地近接③ソーシャルミックス④通学に配慮(63頁)。暑さ対策、寒さ対策(164頁)。特に、結露問題は報道で何度も報道された記憶がある。追い炊き機能も周知された(170頁)のを想起。東大卒、官僚の立場で、総合的な対策を行ってこられた著者の優秀さも全体を読めばわかる。被災者に寄り添う仮設住宅維持のあり方も今後問われる。2013/10/28
もれ
0
東日本大震災で応急仮設住宅の供与にあたった岩手県庁職員(当時)による実務記録。仮設住宅について、わかりやすくまとまった書物がほとんどないので、こうした本が出版されることは今後の対応改善に良い影響があると思う。しかし、ちょっとキレイに書かれすぎているようだ。読んだ印象では、岩手県では割とシステマティックに動いたような印象を抱くが、実際はどうだろうか。2016/11/22
takao
0
ふむ2025/03/21