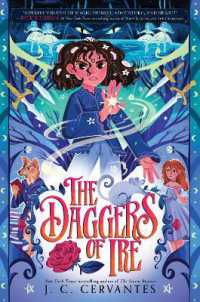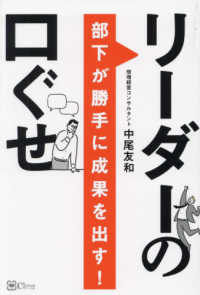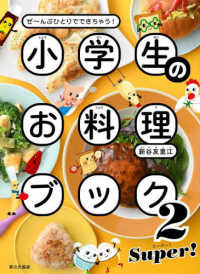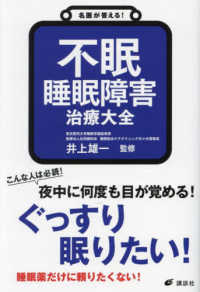出版社内容情報
著者の実践や研究成果そして内外の研究成果を交えながら、場面緘黙の子どもたちが経験する「困った場面」の解消方法や、「話せる」に向けた具体的な支援を紹介する。
内容説明
著者の実践や研究成果そして内外の研究成果を交えながら、場面緘黙の子どもたちが経験する「困った場面」の解消方法や、「話せる」に向けた具体的な支援を紹介。
目次
第1章 場面緘黙の主症状と早期発見(場面緘黙はどういう状態?;場面緘黙の医学的診断基準から学ぶ ほか)
第2章 場面緘黙の症状と状態像の多様性(場面緘黙の症状と状態像の多様性;発話状況は「ちょっとしたこと」で変わる ほか)
第3章 4つの支援と実態把握(場面緘黙の子どもに必要な4つの支援;場面緘黙の子どもの実態把握はなぜ必要か? ほか)
第4章 安心感と活動・授業参加度を高める取り組み(すぐに取り組む4つのこと;担任の先生がキーパーソン ほか)
第5章 話せるようになるための取り組み―スモール・スモール・スモール・ステップ(話せるようになるための「スモール・スモール・スモール・ステップ」;スモール・スモール・スモール・ステップの作り方 ほか)
著者等紹介
園山繁樹[ソノヤマシゲキ]
筑波大学名誉教授、島根県立大学教授。博士(教育学)、臨床心理士、臨床発達心理士、自閉症スペクトラム支援士EXPERT(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひろか
10
紳士な人柄がよく出ている。緘黙という状態はけっこう有名だと思うが、たしかに他の発達障害に比べて、レア。 2022/02/05
いとう
6
他の感想にあるように、スモールステップをさらにスモール、スモールにしていくことに場面緘黙の支援のありか型あるのだろう。しかもそれは、p129にあるように行動上の変化(話せる)だけでなく内面(話せたけど緊張した)も評価に入れ、昇るだけでなく降りることもあるスモールスモールスモールステップとある。 驚いた内容として「発症年齢と認識年齢の解離(p32)」。最大で5歳に発症し、35歳に認識した事例。それほどにまで周囲の誤解(家では話せるから・様子を見ましょう)が強いのだろう。2022/11/25
たらこ
4
場面緘黙支援を学ぶのに、まずはこれ。と言えると思う。2022/05/07
ソーシャ
3
場面緘黙症支援の第一人者である臨床心理士の先生が、場面緘黙症の概念や具体的な支援方法(スモール・スモール・スモールステップ)、事例紹介をわかりやすくコンパクトに纏めた一冊。具体的な治療方法などをよく知らなかったのですが、心理学的なアプローチに加えて教育職の理解と粘り強い支援が欠かせない疾患だという印象を受けました。ところでこの疾患っていわゆる心身症と考えてもいいのでしょうかね…2022/05/01
yucco
2
場面緘黙かなと思われるお子さん(未就園児)に接する機会があり、読んでみました。とにかく焦らず、子どものペースでサポートしていく事が大切なんですね。第5章に示されている事例を読むと、支援する大人達がここまで寄り添える体制を、例えば現在の小中学校などで整備出来るのか…日頃、先生方の多忙さを見聞きしているだけに、実際はなかなか難しいのでは?と思ったりもしました。例え難しくても、子どもの状況や気持ちを理解することは大切。引き続き勉強したいです。2024/08/26