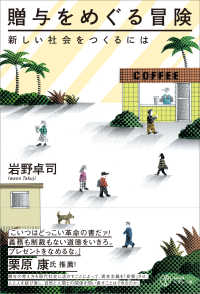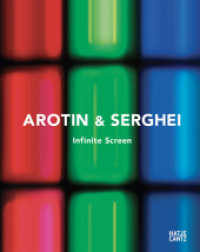出版社内容情報
文科省の「スクールソーシャルワーカー活用事業」が導入されて8年。認知度も上がり,スクールソーシャルワーカーの人数も増加の流れにあります。形だけの展開にならないように,いま一度スクールソーシャルワーカーが何を考え、どのように行動すればいいかを考えるための一冊です。
内容説明
子どもの最善の利益をベースに、スクールソーシャルワークの“いま”を考える。文科省の「スクールソーシャルワーカー活用事業」が導入されて8年。認知度も上がり、スクールソーシャルワーカーの人数も増加の流れにある。形だけの展開にならないように、いま一度スクールソーシャルワーカーが何を考え、どのように行動すればいいかを考えるための一冊。
目次
1章 スクールソーシャルワークの動向と基本的な考え方
2章 子どもの権利と貧困問題
3章 生徒指導とスクールソーシャルワーク
4章 特別支援教育とスクールソーシャルワーク
5章 スクールソーシャルワーカーと教職員との相互作用による子どもと家庭のエンパワメント
6章 子どもを取り巻く地域社会をつむぎ育むスクールソーシャルワーカー
7章 学校事故・事件とスクールソーシャルワーク―校内で起きる「子どもの人権侵害」ケースをどう考えるか?
8章 子どもたちが抱える問題とスクールソーシャルワーク
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
24
この本では、子どもの伴走者としてのスクールソーシャルワーカーのあり方について深く考察されています。子どもの権利条約の時代のなかで、子どもの最善の利益に立つソーシャルワークとはいったい何なのか考えさせられました。また、学校組織のなかにいるワーカーのジレンマについても考えさえられました。完璧なワーカーなどいません。子どもに向き合い、寄り添いながら、専門性を深めていかなければならないのだとも思いました。2016/05/27
🍒
5
スクールソーシャルワーカーはまだまだ認知度が低いけれど、子どもの権利を守るための重要な職業だと思う。また、本書を通して貧困や不登校、特別支援、虐待、いじめ、体罰など子どもや家庭をとりまく生活課題についていろんな視点から学べたので良かった。個人的には、子どもや親に限らず、支援を必要としている人は、自ら助けを求めたり、自分の権利を主張することができない。だからこそ、sswrが教室を巡回したり、課題を抱えてる家庭へアウトリーチすることが重要だし、本人に変わって権利を代弁することが大事なのかなと感じた。2018/12/18
-

- 和書
- ばるのおむかえ