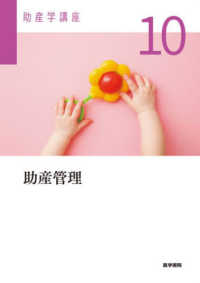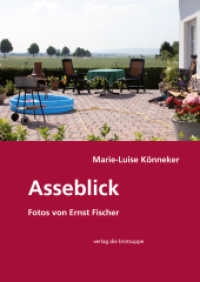- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
内容説明
米国や英国の実践では、早期対応による緘黙状態の改善が明らかになってきました。しかし、日本では場面緘黙の認知が遅れているため、誤解も多く、たくさんの子どもたちが治療やサポートを受けることができず、苦しんでいます。本書は、72のQ&Aをベースに、緘黙経験者や保護者らの生の声などを載せた110のコラム、そして17の具体的な実践で構成され、保護者と教師が場面緘黙を分かりやすく理解するための基本的な情報を網羅しました。
目次
第1章 理解(「場面緘黙」とは?;原因;早期発見・早期対応の重要性)
第2章 対応(子どもの状態を理解する;適切な環境を整える;その子に有効なアプローチを検討する)
第3章 実践―スモールステップの取り組み(保護者と教師との取り組み;教師との取り組み;保護者との取り組み)
著者等紹介
角田圭子[カクタケイコ]
かんもくネット代表。臨床心理士。教育センターの教育相談員、思春期外来や精神科の心理士などを経て、現在、兵庫県にてスクール・カウンセラーや三田市民病院小児科・心理カウンセリングの心理士として勤務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さおり
39
図書館本。園に出向いた時などに相談されることがあるのだけれど、いつもあやふやな知識で対応しちゃっていたため、読んでみました。読んでみて、とりあえずこれまで園の先生方にアドバイスした内容が的外れではなかったことに安心しました。たくさんの当事者や家族の声が載っていて、それも勉強になりました。2017/03/16
しぃ
21
診断された訳ではないけど、学校でも特定の先生や友達としか喋らないと担任の先生から指摘を受け、場面緘黙の可能性を言われました。とりあえずどんなもんかと読んでみましたが、言われてみればそういう子もいたかも。人により差はあるけど、理解のなさに苦しむことがなくなればいい。我が子の場合はとりあえずまだ学校始まったばかりだし、最近は楽しそうに行ってるし、もう少し様子見かなあ。2020/07/12
ねぼ
20
図書館でなんとなく惹きつけられて読むと、かつての私の事ではないか!学校では話すことができなかった時期がありました。学校の先生が家庭訪問をしても同じ。場面緘黙症だそうです。単に内気と大人しいとかではない。ケアを必要とし、早期にケアしないと後遺症が残ると。衝撃的。ケアはしてもらったことないから、私は後遺症中?音楽かスポーツが治療になるとか、転校がきっかけで発話できる場合もある。ピアノを習わせてもらったり、部活で卓球やバレーボールをしたことや、転校もした。。今後、もしかしたら向き合っていった方がいいのかも。2016/05/23
tellme0112
11
いい話もあるけど辛い話も多い。これは普通の子育てにも参考になる。子どもの伴走者としての姿勢。中学年後半からは主体性を本人に持たせる、と強調されていて、こういう姿勢がどの子にも必要なのだと思った。自転車の練習のように。後ろから手で支えて…支援していると分からないように支援する。ちょっと手を離してみる。乗れていても「今できたね!」とは教えず…。こんなさりげなさがいいのね。最後の詩が良い。同級生の中にクラスに一人はいた、しゃべらない子。あれはこういうことだったのか…!やってはいけない対応やってたよ2017/05/20
arina
6
自身が場面カンモクだから 役に立つかと思って さらっと目を通した。本書にあるように 「条件が整っていたら話せる」、「少しは話すことができるから返って理解されにくい」、認知度が低いぶん 説明しても 心の持ちようの問題と軽く捉えられるか 言いわけと思われそうで 説明しようと思えない2017/11/01