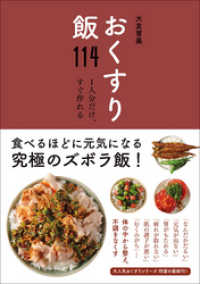内容説明
本書はコンピテンシーをベースとした評価制度の設計方法を中心に、バランススコアカードによる業績評価、ベースサラリーの設計方法等、米国の人事賃金制度について解説したものです。
目次
1 コンピテンシーの基本を押さえておく
2 コンピテンシーを利用した評価制度の作成法
3 ハイパフォーマーとコンピテンシーモデルの関係
4 コンピテンシー・ディクショナリーの事例
5 コンピテンシーをベースにした賃金制度
6 米国型ベースサラリーの作成法
7 コンピテンシーを利用した評価・賃金制度導入事例
著者等紹介
遠藤仁[エンドウヒトシ]
カルク代表取締役・チーフコンサルタント。1961年7月13日生。早稲田大学法学部卒。早稲田大学大学院商学研究科(経営学専攻)修了。マーケティングコンサルティング会社、商社系シンクタンクを経て、’90年大和銀行のシンクタンク大和銀総合研究所に入社。東京本社経営コンサルティング部にて経営コンサルタントとして主にHR(ヒューマンリソース)コンサルティング業務に従事する。’96年同社を退社し、日本ブレーンセンターに入社。副社長兼主席コンサルタントとして、引続き多くの企業のHRコンサルティングを手がけた後、退社。’98年よりHR分野のアウトソーシングとコンサルティングを手がけるカルクに入社、取締役を経て現在代表取締役
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mkt
2
コンピテンシーによる評価制度の全体感が理解できた。米国ベースのため確かに日本での導入はよくよく考える必要があるが、頑張っている人が真っ当に評価されるようになる一つのツールとして理解できてよかった。 20200124読了 303ページ 21分2020/01/24
orataki
0
【第21冊目】執筆のネタに急遽流し読みしました。組織のケイパビリティを高めるには高い業績を叩きだせる人のコンピテンシーを抽出して組織に普遍化させること。業種・業態によって求められるコンピテンシーは異なります。多分、現在の企業はコンピテンシーの抽出まではできているのだと思います。ただ、それを個人の評価に結び付けるところで苦労されているのではないでしょうか。実践例を見ることでヒントが得られると思います。2011/04/16