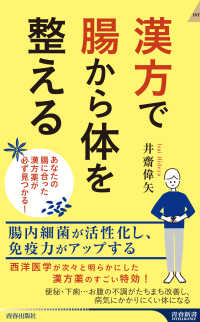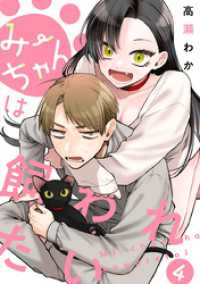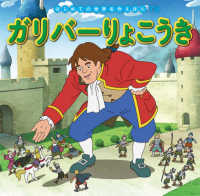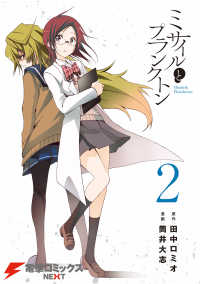内容説明
千家が茶家として大きく展開した近世前期(17世紀~18世紀中期)。利休が大成したとされる茶の湯を、表千家歴代(元伯宗旦、江岑宗左、随流斎、覚々斎、如心斎)は、それぞれの時代の要請に合わせて、どのように創造的に受け継いでいったのか。近年発見・整理された表千家不審菴所蔵の文書史料を用いて、茶会様式の変遷、茶の湯の理念の形成を実証的に明らかにする。
目次
序章 本論の課題と史料の所在(研究史と課題;史料の所在)
第1章 近世前期における表千家の歴史(茶家としての千家の確立;茶の湯支持層の拡がりから家元制度の成立へ)
第2章 茶会記および道具帳に見る茶の湯の変遷(一七世紀中・後期における千家流茶会様式の確立;一八世紀前半期における茶会と道具の特性)
第3章 千家における茶の湯の理念の変遷(一七世紀中・後期における茶の湯の理念の形成;一八世紀前半期における茶の湯の理念の展開)
著者等紹介
千宗員[センソウイン]
昭和45年、京都市に生まれる。本名芳紀。表千家家元後嗣。一般財団法人不審菴副理事長、一般社団法人表千家同門会専務理事、不審菴文庫長。平成5年、同志社大学文学部卒業。同8年、英国バッキンガム大学修士課程修了。同10年2月、大徳寺の福富雪底老師より猶有斎の斎号を授かり、宗員の名を継いで若宗匠の格式を得る。同24年、同志社大学より博士(芸術学)の学位を取得(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たかこ
15
#茶の湯 表千家当代の猶有斎宗匠の博士論文を本としてまとめたもので読み応えあり。千家を継承する方として素晴らしく、尊敬の念しかありません。千利休以降、利休の孫の宗旦、その宗旦の息子たちが今の三千家(表千家・裏千家・武者小路千家)となり…三千家があったからこそ現代まで続いている。江岑宗左の「茶の湯は二十年続けなければならない」、如心斎の「茶の湯の稽古の段階としての「守破離」」どれも先代の流れを組み当代の変化を加え、脈々と受け継がれていく。「淡々として水の流れるがごとく」私もその末端として、稽古にはげみたい。2021/12/13