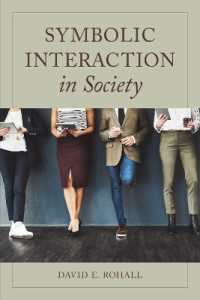内容説明
フロアタイムの「原典」が、ここに復刻!DIRとは、「発達段階(D)と個人差(I)を考慮に入れた、相互関係(R)に基づくアプローチ」のこと。表面上の特徴や行動の変化を目標とせず、子どもの真の発達を促す画期的なプログラム「DIRフロアタイム」の入門書。待望の再出版。
目次
第1部 明るい未来のために―誤解と事実、早期兆候と新しい枠組み(自閉症再考―われわれのアプローチ;ASDやアスペルガー症候群についての誤解と誤診;ASDの早期徴候―乳幼児早期に発見し、関わりを始めるために;ASDの新しい目標―DIR/Floortimeとは?)
第2部 DIRとは?―子どもが周囲と関わりをもち、コミュニケーション能力を伸ばし、思考力をつけていくために家族ができること(家族主導で;注意を向け、関わりをもつために―子どもをみんなの世界に導くには;双方向コミュニケーションと問題解決能力を身につける;シンボル、考え、言葉;論理的な考え方と現実の世界;抽象概念と深く考える力;生物学的特徴(1)五感を通じて世の中を経験する
生物学的特徴(2)視覚と聴覚に問題がある場合)
第3部 Floortime(Floortime―家庭でのアプローチ;Floortimeとは? ほか)
第4部 DIRによるアセスメントと療育(DIR/Floortimeによるアセスメント;DIR/Floortimeによる包括的療育プログラム;教育プログラム―考える力、コミュニケーション、学力を伸ばすために)
第5部 問題行動への対応(お決まりの台詞とエコラリア;自己刺激行動、刺激への強い欲求、過活動、回避行動;日々の問題点―食事、トイレ・トレーニング、衣服の着脱など;問題行動;感情のコントロール;気持ちの崩れと退行;ソーシャル・スキルを伸ばすために)
著者等紹介
グリーンスパン,スタンレイ[グリーンスパン,スタンレイ] [Greenspan,Stanley]
ジョージ・ワシントン大学の精神医学、行動科学、小児科部門の臨床教授。Floortime Foundationの設立者。発達および学習障害に関する学際的協議会(Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders)の会長、および「3歳までの精神保健と発達障害の診断基準(Zero to Three)」の創立会長でもある。長年の児童精神科疾患の研究に対して、アメリカ精神科協会の最高の名誉であるIttleson Prizeをはじめとする、さざままな賞を受賞。40近い著作があり、12力国以上で幅広く紹介されている。2010年没
ウィーダー,セレーナ[ウィーダー,セレーナ] [Wieder,Serena]
Journal of Developmental Processesの准編集者
広瀬宏之[ヒロセヒロユキ]
横須賀市療育相談センター所長。1969年東京都生まれ。1995年に東京大学医学部医学科を卒業、同小児科に入局。1999年より2003年に同大学院で小児神経学の研究を行い、2003年から2007年まで、国立成育医療センターこころの診療部発達心理科にて、自閉症と子どものこころの臨床に従事。2006年から2007年にかけてフィラデルフィア小児病院にて、子どものこころの研修システムの日米比較研究を行う。2008年春より現職。医学博士、小児科専門医、小児神経専門医、小児精神神経学会認定医、子どものこころ専門医。専門は発達障害の地域支援(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
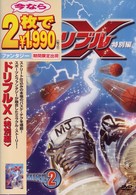
- DVD
- ドリブルX <特別編>