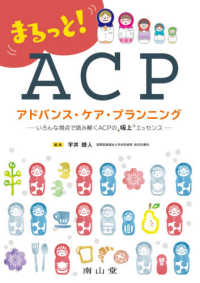- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
海難事故、入水自殺、人命救助…そして3・11東日本大震災。海からいくつもの“魂”を救い続けた潜水士の苦闘を描くドキュメント。
目次
プロローグ
第1章 呼吸する者、しない者
第2章 遺体に育てられた男
第3章 蜘蛛の糸
第4章 波打ち際の夏
第5章 破滅の午後
第6章 暗い運河の水底へ
第7章 群青色の境界
エピローグ
著者等紹介
矢田海里[ヤダカイリ]
1980年、千葉県市川市生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒。在学中、イラク戦争下のアメリカ合衆国を自転車横断しながら戦争の是非を問うプロジェクト“Across‐America”を行い、この体験を文章にまとめた「アクロス・アメリカ」を執筆、雑誌『かがり火』に連載。また2011年以降、マニラのストリートに暮らす人々を見つめるドキュメントの制作にも着手。以降、人の内面の光と影を追いながら取材活動を展開。東日本大震災直後に現地入りし、現地に居を構えながら被災した人々の声を拾う活動を続ける。ユネスコなどと共同し、全国で震災写真展を16回開催。放送批評雑誌『GALAC』に「東北再生と放送メディア」を29回連載。スポーツ・冒険マガジン『ド級!』でエクストリーマーの一人に選ばれる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
118
主人公は潜水士、場面は東日本大震災後の運河から始まる。ドライスーツを装着して行方不明者を捜索する。彼の生い立ちや家族、潜水士の仕事について、遭難者や行方不明者を捜索するということ、その仕事で起きる葛藤他、彼の人生とともに語られてゆく。あの震災、津波はテレビで生で見ていた者にとっては悪夢といえばそれだけだが実体験された人にとっては未だにやりきれない思いでいっぱいだと思う。変わり果てた遺体の引き上げに臨む主人公の心情がしっかりと描かれている。図書館本2021/06/01
そら
71
潜水士、吉田浩文さんの実録の物語。父親も潜水士だった吉田さんが土木潜水士から警察などに協力する個人の遺体捜査のダイバーになった経緯が書かれている。身の危険すらある現場を信念を持って挑む姿に引き込まれる。せっかく遺体を見付けても、遺族から捜索費用を踏み倒されたり値切られたり、どんな時もお金と人はトラブルが付き物なんだなぁと思ってしまう。震災の現場の章は胸が痛んだ。北海道の遊覧船沈没の行方不明者も、吉田さんのようなダイバーたちが今も探しているのだろうか。家族の心情が伝わってくる。早く見つかって欲しい。2022/05/08
つちのこ
44
凄まじい生き方の、男の人生を見た思いだ。ダイバーの吉田浩文氏は震災後すぐに津波被害者の遺体引き上げ作業を行った人物である。仙台港に沈んだ自殺者や遭難者の遺体引き上げを手伝うちに、いつしか本業を圧迫し、倒産の憂き目に遭う。遺族から捜索費用を回収することができず負債が膨らんだことによるが、そんな苦境をものともせずに暗い海底に向かっていく。津波被害者の捜索でヘドロの海に潜る姿は、もはや使命感を超越している。この勇気と意地はどこからくるのか。粗い文章に不満は残るが、海に生きる真の男の強さを知った一冊であった。 2021/11/24
読特
37
潜る、探す、引き上げる、類まれな才能。筋を曲げない頑固さ、正義感。高校中退、母親との確執、家出。三度の離婚と四度の結婚。遺族とのけんか、元請会社との諍い。倒産、破産、車上生活。不器用な生き方、発達障害を思わせる人物像、慕う若者がいる。311、自らの危険を顧みずに果たした人命救助。復興。忘れられていく犠牲者たち。探し続ける。まだ待っている遺体がある。彼の功績に我々の社会は十分に報いているだろうか。才能を存分に発揮するだけの環境を与えているだろうか。遠くから緊縮財政が罪を犯す。50歳を過ぎ、波乱万丈は続く。2021/04/21
shikada
34
入水自殺や津波に持っていかれた方の遺体を引き上げる潜水士に密着取材したノンフィクション。遺体と向き合い続けるうちに精神が不安定になったり、潜水病に冒されたり、引き上げに要した費用を遺族が払えず肩代わりしたり、とにかく苦難の連続。この潜水士の方に引き上げを委託していた行政サイドは、潜水士の方の厚意に甘え過ぎでは…。3.11で自身も被災しながらも、遺体引き上げに携わり続けて、きっと救われた人は多いだろうと感じる。決して軽いテーマではないけど、すっと入ってきて引き込まれる文章だった。2021/03/28
-

- 電子書籍
- くずヒーローは要りません!~男運ゼロ令…