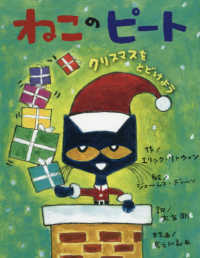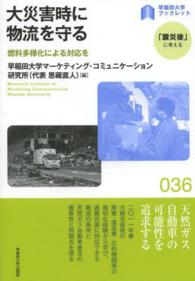- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
目次
動物園への旅
生きている島々
見たいと思った人々
体を造るものたち
諸条件が適用される
病めるときも健やかなるときも
長いワルツ
お互いの成功を保証しあう
大きな進化は速いテンポで
微生物アラカルト
微生物研究の未来
著者等紹介
ヨン,エド[ヨン,エド] [Yong,Ed]
サイエンスライター。アトランティック誌のスタッフライター。ブログの「Not Exactly Rocket Science」は、ナショナル・ジオグラフィックが運営している。ニューヨーカー、ワイアード、ニューヨークタイムズ、ネイチャー、BBC、ニューサイエンティスト、サイエンティフィック・アメリカン、ガーディアン、タイムズなどにも寄稿している。ロンドンとワシントンDCに在住
安部恵子[アベケイコ]
慶應義塾大学理工学部物理学科卒業。電機メーカーで製品開発などに従事したのち、翻訳業。ノンフィクションの書籍を中心に翻訳や翻訳協力などをしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
29
細菌学(研究)は、今、科学に関し一番ホットな分野の一つではなかろうか。出産に際し、母から子へマイクロバイオームを移すとか、腸内環境を整えるため、健全な人の糞便を採取し、不調な人の腸に直接移植する、あるいは経口で移すといった、一部で話題になっている研究についても、その研究や治療の現況を丁寧に教えてくれている。 取材の幅広さ、ホットさ、丁寧さは、エド・ヨン氏ならではのものだろう。2018/01/14
GASHOW
8
アリとアブラムシの関係は共生としられる。人間と腸内細菌も共生なのかもしれない。母乳に含まれる成分が3種類あるがそのなかにオリゴ糖が含まれているという。オリゴ糖は人間は消化できない腸内細菌のエサとなる。腸内細菌を人が知るのは糞便なので、医療としていかすのには抵抗がある。科プレセルにいれて飲み薬としての調査はされている。野生生物は子供の糞をたべることや親の肛門をなめるなども細菌の活用なのかもしれない。2017/07/10
河童
3
細菌の研究がかくもさまざまな範囲でなされていることもびっくりですが、それらを全般にしかも詳細にわかりやすく記してくれて、読んでいて楽しい本でした。2017/07/28
ジコボー
2
動物たちは、なぜ、自身の生存発達に必要な機能を微生物にアウトソーシングしているのか?なぜ自分で行わないのか?この本に一つの答えが書かれていました。 「そうせざるを得ない」という事です。私たちの祖先が生まれたとき、それらはすでに地球を埋め尽くしていました。生まれた瞬間からそれが存在しない事があり得なかったのです。なるほどと、附に落ちました。 世界は昔も今も微生物に支配されています。しかし、普通、私たちには見えないし気付きもしません。もしかすると、別の尺度で見れば、私たちの存在も同様なのかもしれません。2019/12/07
y
1
近頃、微生物関係の本をよく読んでいるので、目新しいトピックスはそれ程ありませんでした。 でも、一歩引いた目線でそれぞれの研究成果を紹介し、世間で言われている夢のような効用について、何が正確で、何が証明されていないのか、誠実に説明しているなと感じました。 しかし、ちょっと長かった…2017/10/23
-

- 電子書籍
- 妹の迷宮配信を手伝っていた俺が、うっか…
-

- 電子書籍
- ガンスリンガー・リプレイス(21) C…