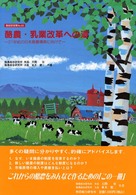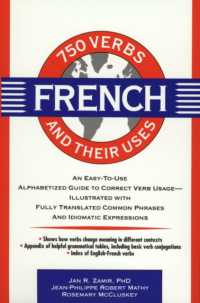出版社内容情報
歌舞伎研究に民俗学の成果をとりいれ、新しい研究方法を確立。歌舞伎の生きた芸能に迫り、歌舞伎本来の力を近代の知性から解放するという画期的な仕事を成し遂げた郡司正勝。刪定集未収録原稿をまとめた貴重な著作集。研究者(演劇・国文学)、日本舞踊・歌舞伎・演劇関係者必読!
▼郡司正勝(ぐんじ まさかつ)=1913年北海道生まれ。1939年早稲田大学国文科卒業。早稲田大学名誉教授・舞踊学会名誉会長。著書に『おどりの美学』『かぶきの美学』『かぶき様式と伝承』『かぶき論叢』『童子考』『和数考』『郡司正勝刪定集』(全6巻)他多数。1998年4月逝去。
主要目次
Ⅰ 芸能の足跡/近世演劇の誕生/劇場を読む/江戸の発想/歌舞伎と能の変身・変化/歌舞伎演出のなかの儀礼/元禄歌舞伎が生んだ「打擲事」 Ⅱ 黒衣論――黒は影か/歌舞伎衣裳の色彩/かぶき台本の性格/芝居の台帳の性格/かぶきの稽古について/かぶきの正月/かぶきの桜/水を見せる道具仕立/歌舞音曲の間/役者と役者絵/浮世絵から写真へ Ⅲ 大石内蔵助の虚像と実像/「仮名手本」の二人の不義士/「悪婆」と「毒婦」/田之助と悪婆時代/外郎売と御霊神/お七曼陀羅/幽霊は壁を通る/日本の亡霊/幽霊の故郷 Ⅳ 能とそのあとに来るもの/日本最古の舞踊/国風の歌舞のこと/日本の仮面と舞踊/日本の「地獄」の芸能/「老い」のかたち/見せるものではない盆踊/アジア芸能圏のなかの日本の伝統芸能 Ⅴ 偽りの山/花鳥風月の系譜/江戸の芸術/廓のこと/江戸時代の中国劇の知識/日本の「三国志」/雛の位置/四季の源流/忘れゆく美 Ⅵ かぶき道――私の中の歴史
内容説明
昭和戦後の歌舞伎研究に画期的な方法を導入して幾多の成果を挙げ、“郡司学”とまで称された著者晩年の豊かな穣りの景色。待望の遺稿集。歌舞伎を軸に古代の舞踊から能や民俗芸能、また日本文化の心意伝承に及ぶ珠玉の論考を一巻に。
目次
芸能の足跡
近世演劇の誕生
劇場を読む
江戸の発想
かぶきと能の変身・変化
かぶき演出のなかの儀礼
元禄江戸かぶきが生んだ「打擲事」
かぶきと色子
黒衣論―黒は影か
歌舞伎衣裳の色彩〔ほか〕
著者等紹介
郡司正勝[グンジマサカツ]
1913年(大正2年)北海道札幌市に生まれる。早稲田大学文学部を卒業の後、早稲田大学演劇博物館員・講師・助教授・教授を経て退職、名誉教授。1963年より歌舞伎の演出・監修に携わる。1998年(平成10年)、札幌にて死去、84歳
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。