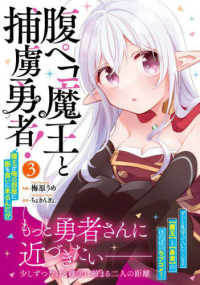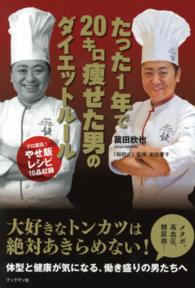- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学一般
出版社内容情報
図書館のはたらきを通して学校教育を変える、教育の変革を促進する。学校図書館はどうあるべきなのか、学校図書館が教育においてもつ可能性「教育力」について、教育科学の諸領域を専門とする5人の研究者(図書館情報学・教育史・教育メディア・教育法学・教育行政学)が論じる。
内容説明
学校図書館のもつ「教育力」を問う。自ら学び、自ら考える子どもを育む学校教育のあり方を探る。
目次
第1章 いま、なぜ学校図書館を問うのか
第2章 学校図書館と教育の変革
第3章 期待と信頼を寄せる学校図書館―実践校にみる課題
第4章 読む権利を保障する学校図書館と学力
第5章 学校図書館職員の現況と将来像
第6章 学校図書館を支える教育行財政のあり方
終章 私たちの提言―あとがきを兼ねて
著者等紹介
塩見昇[シオミノボル]
1937年生。図書館情報学専攻。京都大学教育学部卒業後大阪市立図書館勤務(司書)。大阪教育大学教授、附属図書館長を経て同大学名誉教授。日本図書館協会理事長、日本図書館研究会理事長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
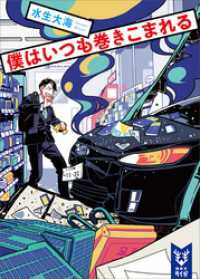
- 電子書籍
- 僕はいつも巻きこまれる 講談社タイガ
-

- 和書
- 経営戦略と競争優位