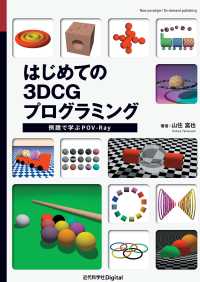出版社内容情報
喜び,驚き,嫌悪,怒り,悲しみ,恐怖……人はさまざまな感情を持つ.このような感情はどこから生まれ,成長のどの段階で持つようになるのか.人以外の動物にも感情はあるのか.人の行動に感情が果たす役割とはいったい何か.長年精神科診療に携わり,脳研究も手掛けてきた著者が,感情とは何かという問いを,発達心理学,脳科学,精神医学,さらには社会学の知見を駆使し掘り下げる.分断や対立が深刻化する現代,人を行動に駆り立てる感情について知ることの重要さは増すばかりだ.
【目次】
第1章 感情とは何かを考える
一 感情とは何か?
二 情動と感情と気分
三 社会脳
四 社会脳の機能と情動
五 間主観性について
六 感情・情動の進化論的研究
コラム1 感情についてどこで勉強できますか?
第2章 発達心理学から見た感情
一 新生児~三か月
二 三~六か月
三 六か月~一歳
四 一歳~一歳六か月
五 一歳六か月~二歳
六 二歳~三歳
七 三歳~四歳
コラム2 感情についてどんな学会で研究されていますか?
第3章 脳科学から見た感情
一 ヒトを用いた脳研究の歴史
二 損傷脳研究とは?
三 脳画像研究とは?
四 ポジティブ感情の脳画像研究(メタ解析と系統的レビュー/音楽、食事、金銭/ユーモアなど)
五 ネガティブ感情の脳科学研究(不安/恐怖/怒りと攻撃性/寂しさ)
六 感情調節の脳科学研究(感情調節の手法/感情調整で活動が変化する脳領域)
七 扁桃体と情動(症例S.M./扁桃体の脳画像研究/扁桃体と前頭葉の相互作用/情動、脳機能、環境の相互作用モデル)
コラム3 感情はどのように研究されているのですか?
第4章 こころの病気における感情
一 統合失調症(古典的な研究から/クレペリン以前の考え方/クレペリンによる感情障害/クレペリン以後の考え方/古典から近代に至る視点/統合失調症における感情障害)
二 統合失調症における最新の研究(陰性症状と感情障害/感情の認知と制御/抑うつ/脳機能障害/最新の知見による統合失調症の感情障害)
三 ひねくれとわざとらしさについて(古典におけるひねくれとわざとらしさ/社会現象としてのひねくれとわざとらしさ/現代社会の統合失調症らしさ)
コラム4 感情や気分の病気にはどんな治療方法がありますか?
第5章 社会現象における感情
一 ジョージ・オーウェル『一九八四年』(時代と統合失調症的心性)
二 うつ病的時代背景(日本人の死生観/歴史的経過/JAPAN '97 & '98/一九九七年のできごと/社会的様相)
コラム5 顔の認知について教えてください
第6章 感情と情動の3Dモデル
一 ここまでのまとめ
二 対人関係と感情表出
三 同調性と分裂(失調)性の2Dモデル
四 快楽性を加えた3Dモデル
五 結局のところ感情とは何なのか?
コラム6 AIと感情
内容説明
喜び、驚き、嫌悪、怒り、悲しみ、恐怖…人はさまざまな感情を持つ。このような感情はどこから生まれ、成長のどの段階で持つようになるのか。人以外の動物にも感情はあるのか。人の行動に感情が果たす役割とはいったい何か。長年精神科診療に携わり、脳研究も手掛けてきた著者が、感情とは何かという問いを、発達心理学、脳科学、精神医学、さらには社会学の知見を駆使し掘り下げる。分断や対立が深刻化する現代、人を行動に駆り立てる感情について知ることの重要さは増すばかりだ。
目次
第1章 感情とは何かを考える
第2章 発達心理学から見た感情
第3章 脳科学から見た感情
第4章 こころの病気における感情
第5章 社会現象における感情
第6章 感情と情動の3Dモデル
著者等紹介
飯高哲也[イイダカテツヤ]
1984年、筑波大学医学専門学群卒業。トロント大学、福井医科大学、名古屋大学情報文化学部、名古屋大学大学院医学系研究科などを経て、名古屋大学脳とこころの研究センター教授を務めた。博士(医学)。名古屋大学名誉教授。専門は、精神医学、神経科学、脳画像研究など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
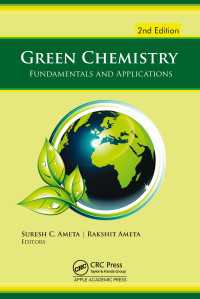
- 洋書電子書籍
- Green Chemistry, 2n…