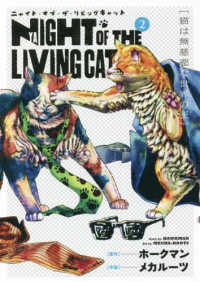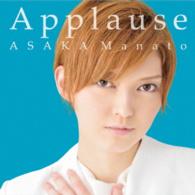出版社内容情報
アインシュタインはまちがっていたのか!? 物理学革命の立役者が頑固な反対者になった理由とは
序章.古典論の危機と量子論の誕生
I部 量子論の創始者としてのアインシュタイン
1.アインシュタインによる革命……粒子としての光
2.ボーアによる革命……飛躍する量子
3.アインシュタインによる二度目の革命……因果律の危機
<コラム>アインシュタインvs.ニュートン
II部 量子力学の誕生
4.量子力学の完成……ついに全貌を見せた新しい力学
5.不確定性関係の発見……位置と運動量は同時に測定できない
6.相補性概念の発見……測定装置と対象は切り離せない
<コラム>アインシュタインvs.マッハ
III部 量子力学の反対者としてのアインシュタイン
7.可動式二重スリットの思考実験……不確定性関係は成り立っているか
8.光子箱の思考実験……相互作用なしで測定は可能か
9.EPRの思考実験(1)……量子力学は完全か
10.EPRの思考実験(2)……自然界に非局所性はあるのか
<コラム>アインシュタインvs.ヒューム
IV部 アインシュタインはまちがっていたのか
11.多世界解釈と軌跡解釈……量子力学の解釈のさまざまな試み
12.時間対称的な解釈……過去と未来が現在を決める
※ブックガイド/付録解説/参考文献リスト
内容説明
アインシュタインは本当にまちがっていたのか!?天才物理学者が生涯をかけてつらぬいた量子力学批判。その意義を問い直し、新たな解釈に挑む。量子力学は不完全なのか。量子力学は実在の世界をとらえているか?
目次
古典論の危機と量子論の誕生
第1部 量子論の創始者としてのアインシュタイン(アインシュタインによる革命―粒子としての光;ボーアによる革命―飛躍する量子;アインシュタインによる二度目の革命―因果律の危機)
第2部 量子力学の誕生(量子力学の完成―ついに全貌を見せた新しい力学;不確定性関係の発見―位置と運動量は同時に測定できない;相補性概念の発見―測定装置と対象は切り離せない)
第3部 量子力学の反対者としてのアインシュタイン(可動式二重スリットの思考実験―不確定性関係は成り立っているか;光子箱の思考実験―相互作用なしで測定は可能か;FPRの思考実験その1―量子力学は完全か;FPRの思考実験その2―自然界に非局所性はあるのか)
第4部 アインシュタインはまちがっていたのか(多世界解釈と軌跡解釈―量子力学の解釈のさまざまな試み;時間対称的な解釈―過去と未来が現在を決める)
著者等紹介
森田邦久[モリタクニヒサ]
1971年兵庫県生まれ。大阪大学基礎工学研究科・文学研究科修了。博士(理学)と博士(文学)を取得。早稲田大学高等研究所准教授などを経て、2013年から九州大学基幹教育院准教授。専門は科学哲学、科学史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 声優ラジオのウラオモテ #02 夕陽と…
-
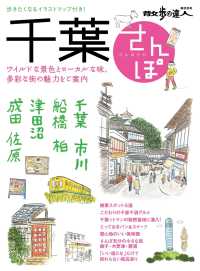
- 電子書籍
- 千葉さんぽ 散歩の達人MOOK