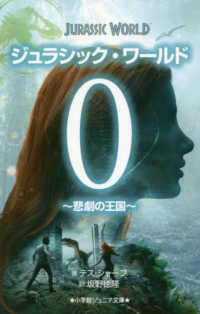出版社内容情報
道徳は何に由来するのか.良心?宗教?あるいは脳内の化学物質か? 心の哲学のパイオニアである著者が,脳科学の最新の成果を踏まえ,道徳の生物的起源を明らかにする.人間はまず自らを気遣い,愛着によって子供を気遣い,連れ合い,近親者,他人へと気遣いを広げ,人間一般での信頼が形成される.この気遣い,愛着,信頼を生み,制御しているのが神経伝達物質のオキシトシンであり,著者はここに道徳の基盤を見る.今や哲学は限りなく科学に接近している.
第1章 序論
第2章 脳に基盤をもつ価値
第3章 気遣いと世話
第4章 協力することと信頼すること
第5章 ネットワーキング??遺伝子,脳,行動
第6章 社会生活のためのスキル
第7章 規則としてではなく
第8章 宗教と道徳
【著者紹介】
Patricia S. Churchland
内容説明
われわれの道徳観は何に由来するのか?良心、宗教、それとも脳内ホルモンか?脳科学や進化生物学の最新の成果を取り入れ、心の哲学のパイオニアが人間の本性に大胆に切り込む。
目次
第1章 序論
第2章 脳に基盤をもつ価値
第3章 気遣いと世話
第4章 協力することと信頼すること
第5章 ネットワーキング―遺伝子、脳、行動
第6章 社会生活のためのスキル
第7章 規則としてではなく
第8章 宗教と道徳
著者等紹介
チャーチランド,パトリシア・S.[チャーチランド,パトリシアS.] [Churchland,Patricia S.]
カリフォルニア大学サンディエゴ校哲学名誉教授、ソーク研究所非常勤教授。著書にBrain‐Wise(邦訳『ブレインワイズ脳に映る哲学』)、Neurophilosophyがある
信原幸弘[ノブハラユキヒロ]
1954年生まれ。1983年、東京大学大学院理学系研究科科学史・科学基礎論専攻博士課程単位取得退学。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授。専門は心の哲学
樫則章[カタギノリアキ]
1956年生まれ。1987年、大阪大学大学院文学研究科哲学・哲学史専攻博士課程単位取得退学。現在、大阪歯科大学歯学部教授。専門は倫理学
植原亮[ウエハラリョウ]
1978年生まれ。2008年、東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻博士課程修了。現在、関西大学総合情報学部准教授。専門は哲学・脳神経倫理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
GASHOW
Yoshi
ソーシャ
デビっちん