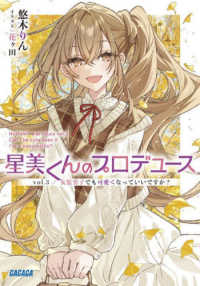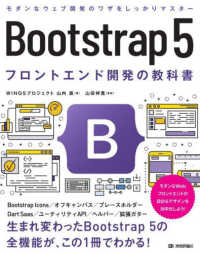出版社内容情報
1章 ある錯覚の歴史
2章 目的なき生
3章 サインはいたるところに
4章 奇妙なのは心の不死
5章 神が橋から人を落とす時
6章 適応的錯覚としての神
7章 いずれは死が訪れる
内容説明
なぜ人生に運命を感じるのか、なぜ死んでも心は残ると思うのか、なぜ自然現象に意味を見出してしまうのか、進化心理学が解き明かす神と宗教の起源。
目次
1章 ある錯覚の歴史
2章 目的なき生
3章 サインはいたるところに
4章 奇妙なのは心の不死
5章 神が橋から人を落とす時
6章 適応的錯覚としての神
7章 いずれは死が訪れる
著者等紹介
ベリング,ジェシー[ベリング,ジェシー][Bering,Jesse]
コラムニスト・ライター・研究者。1975年アメリカ生まれ。ルイジアナ大学ラファイエット校でチンパンジーの認知研究で修士号、フロリダ・アトランティック大学で発達心理の研究で博士号を得た。2002年からアーカンソー大学の実験心理学の准教授、2006年から11年まで北アイルランド・ベルファストのクイーンズ大学の認知文化研究所の准教授を務めた。2011年、執筆活動に専念するために大学を離れ、現在はニューヨーク州・イサカに在住
鈴木光太郎[スズキコウタロウ]
新潟大学人文学部教授。専門は実験心理学。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
23
人は利己的に行動する。自分(と僅かな周囲の人間)以外のことなんて本当は知ったことじゃないというのが生物としての本来のスタンスなのかもしれないけれどそれでは人間が発明した社会というシステムは成り立たない。だから超越者を生み出し彼らがジャッジしていると考えるようになった。神様だって一神教の神様と僕たちの暮らす日本におられる八百万の神様とでは意味合いが全く異なるので同じように考えるわけにはいかないけれど面白かった。アニミズム的な思考から生まれた神様と社会秩序の維持のために生まれた神様。そりゃ反りは合わないよな。2018/08/19
月をみるもの
14
よく「西洋では神と個人が直接対峙することで明確な善悪の観念が生まれるのに対して、日本には世間の価値観に反することを避けようとする相対的な『恥』の文化しかない」とか言われるが、じつはこの二つはどちらも「心の理論」から生じているらしい。意味のない偶然の背後に「物語」を求めてやまないヒトの認知の歪み。それを純化し結晶化させたものが「神」なのだとしたら、まさに「信仰=本能」だよな。。2020/06/18
ヨミナガラ
13
“私たちには心の理論があるため、そしてとりわけ目的論的推理が勝手にはたらくため、人間という存在をこのような意図の観点から見ないようにするのは、きわめて難しい。私たちが道徳的なのは道徳には機械論的・進化的に意味があるからだと考えることは、私たちが道徳的なのは私たちが道徳的だからだと言っているだけのことだ。それは、特別なやり方で行為するように私たちを造った神――神は何もかも知っていて、もし私たちが神の定めた人間性のルールを破ろうものなら、失望して怒るのだ――から権限を奪いとるという点では、十分ではない。”2014/10/30
tama
8
県立図書館からお取寄せ 著者訳者双方が原因で読みづらかった。不要な修飾辞がない論文的書式の方が分かりやすい。訳者もそう心掛けてほしい。でも面白くてポストイットだらけになった。心の理論って知らなかったがwikiにも出てる。忖度能力もその一つ。それと言葉⇒噂話で自分の「知られたくない事」が広まり性交可能性が激減する恐れ⇒欲求の抑制。「見られるとヤバいこと」を「している自分」を見てるかもしれないヤツの存在⇒適応的錯覚!。ちょっと結び付けが急ぎ過ぎてる感強いけどすごく面白い。2020/06/09
やす
6
脳生理学的に、進化論的に、文化人類学的に人はなぜ神を信じるのかを説明した本。こういったことにタブーのある西洋ならではの分厚い記述。脳科学系の本はちょっとした実験をフレームアップするので冗長になりがちだか、これに宗教が絡むと余計冗長。まとめると人類は1.他者には意識があると考える。意図を汲む。2.人生には目的があると考える。3.あらゆること(自然現象についてさえ)意図・理由があると考える。4.他者が他界していても生きているかのように考える。5.説明のつかないものは神のせいにしたい。6.神がいるという錯覚は2014/09/01
-
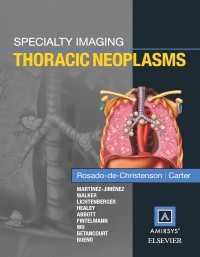
- 洋書電子書籍
- Amirsys専門画像診断:胸部腫瘍<…