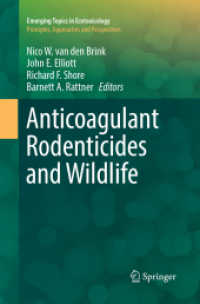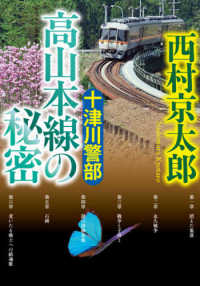感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
52
著者は、「Biogeography&Systematics」誌の編集委員で、ニューヨークのバッファロー科学博物館科学研究員のデニス・マッカーシー氏。シロクマは北極にいてペンギンは南極にいて、お互いが自然な状態で出会うことはないがそれはなぜか?南アメリカとアフリカは昔くっついていた?、シャチはアザラシの子どもを捕まえても元の場所に返すことがあるのはなぜか?、アマゾンが生物の宝庫なのはなぜか?、ハワイにアリがいないのはなぜか?など、「生物地理学」がこうした疑問を解いていきます。2024/04/09
yamakujira
6
タイトルを見ると動物の雑学的な内容を想像してしまうけれど、生物の進化や分布が大陸移動説の根拠になるという壮大な生物地理学の入門書だ。メソサウルスの化石、現生淡水魚アプロケイルス、海産ナマズなどの分布が、今は離れている大陸同士が接していたことを裏付けっておもしろい。もはや生物学の常識になっている進化論は人類にも適用できるのに、人類を研究対象にしたとたん「右翼の狂信的差別主義者と左翼の過激な平等主義者の狭い道を通り抜けなければならない」って現実は、人類の進化が歪んでいる傍証のようで情けない。 (★★★☆☆)2019/07/28
ZEPPELIN
6
生物の多様性を考えるには、進化論と大陸移動説を合わせた生物地理学を知る必要がある。生物が種分化するだけでなく、遥か昔に超大陸が分離したと考えないと説明がつかないことも多い。しかし今も創造論の勢いが強いという状況に著者も一苦労。意外だったのは、進化はゆったり進むということ。今まで突然変異がカギだと聞かされてきたのは何だったのか。地球温暖化による氷河の減少についても、そもそも氷河は生物にとって死を意味し、生物多様性を阻害する最大の要因だと指摘。やはり科学も疑ってみる必要ありと再確認2015/06/20
ビリー
4
生物地理学の本。うん、やっぱりこの手の本は好きだ。進化論や大陸移動説からスタートして動植物の分布や進化を説明し、『銃・病原菌・鉄』の流れを組む民族学的なところまでを一気に駆け抜ける。分量も多すぎず少なすぎず、ちょうど良い。惜しくらむは"インテリジェント・デザイン説"を否定することに対してやや感情的すぎるところかな。たしかに最近は進化論を学校で教えちゃダメになったり、嫌な時代になったけど。そもそも警鐘を鳴らす意味で書かれた本なのかもしれない。2015/01/16
rivaner
2
同じ極地なのに、なぜシロクマは南極にいないのか。なぜペンギンは北極にいないのか。サムシング・グレートがそれぞれの生物がそれぞれに適応して生きていける場所に配置したという説の問題点を生物地理学という考え方で説明してくれる。新たな考え方を展開しているわけではないけど、分かりやすく説明してくれる。本の厚さも適度で飽きずに読めます。2012/03/10
-

- 和書
- 菅原道真事典