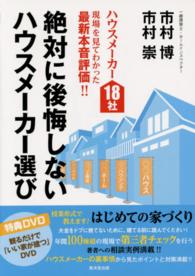内容説明
1968年、いわき市の鈴木直さんから国立科学博物館に手紙が届いた。複数の骨の化石を採集したという。現地へ向かった二人の研究員が発掘した化石は、フタバスズキリュウとよばれ親しまれてきた。以来38年―。このクビナガリュウの学名が決まった。フタバサウルス・スズキイ。当初考えられたとおり、新属新種だった。本書は、日本初のクビナガリュウ発掘、復原、そして種の同定までの軌跡をたどる。
目次
プロローグ 一通の手紙
第1章 第一次発掘、始まる
第2章 第二次発掘、そして一般公開へ
第3章 フタバスズキリュウの骨格復原への道
第4章 フタバスズキリュウはどんな生き物だったか
第5章 ネッシー、ニューネッシー、シーラカンス
第6章 日本でみつかった恐竜たち
エピローグ フタバスズキリュウからフタバサウルス・スズキイへ
著者等紹介
長谷川善和[ハセガワヨシカズ]
1930年長野県生まれ。55年横浜国立大学学芸学部卒業。国立科学博物館研究員、横浜国立大学教育学部教授を経て、現在、群馬県立自然史博物館館長。理学博士。専門は古脊椎動物学(ナウマン象、恐竜、ペンギンもどきなど)。これまでに採集・発掘した15,000点を超える化石は「長谷川コレクション」としても知られ、博物館で展示された(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
毒兎真暗ミサ【副長】
24
昭和43年。恐竜が大好きな鈴木君が福島県のとある地層でナニカの化石を発見した。そこから著者とタッグを組み〈新恐竜〉の存在を証明するため悪戦苦闘する遡り観る恐竜冒険譚。恐竜は【クビナガリュウ】しかも新種。見所は骨格を繋げる過程、標本の復元。38年の時を経てスケールは世界級に広がる。2人の情熱を乗せて体を燻らすその姿は科学博物館にて。https://www.tokyoupdates.metro.tokyo.lg.jp/post-236/ 本書にある腹に刺さるサメの牙、宮沢賢治の恐竜愛も必見。化石発掘誘惑本。2023/05/30
ふたば
11
フタバスズキリュウの発見から、新属新種であると証明されるまでをまとめた一冊。 新属新種であることは発見、発掘された当時から予想されていたことなのだということを、今回この本で知った。多くの部分が発掘されながら、肝心な部分が無かったことと、人的、時間的、予算的なモノをクリアすることが難しく、38年と言う時間が必要となった。これまで日本では発見されてこなかった大物だけに、失敗も多くあったようだ。コツコツと倦むことなく研究を繋げた研究者にも、若い研究者のひたむきな努力にも、敬意を惜しまない。2023/04/24
七月せら
6
化石や古生物と聞くとわくわくしますが専門書を読むほどの知識はとてもないので、こういう専門知識を取り入れつつも一般向けに書かれた本はとても面白いです。たった一個の骨の欠片からでもどんな生物だったのか、どんな風に生きていたのか推定してしまう古生物学の分析力と想像力は素晴らしい。発見された化石が博物館に展示されて大勢の人の興味を喚起する裏には、たくさんの職人技的な努力がなされている。その部分にももっと脚光が当たればと思います。2016/04/24
ゆーき
5
フタバススズキリュウの発掘・調査を記録した本。古生物にはロマンがありますね。 いわき市の双葉層郡で発見/モササウルス/プレシオサウルス/エラスモサウルス/ヒドロテロサウルスの骨格複製品を参考にフタバススズキリュウの骨格を複製/首長竜はプリオサウルス型とプレシオサウルス型に分かれる2015/09/25
半木 糺
4
日本の古生物ファンなら誰もが知っているフタバスズキリュウの発掘経過が記されている。当時少年だった鈴木直氏の名前がこのような形で残るとは、当の本人も予想していなかったであろう。本文中にも例が多いが、アマチュアの化石採集家が大きな業績を残す可能性が大きいのも発掘や古生物学の大きな魅力である。2013/08/05
-

- 電子書籍
- 最低ランクの冒険者、勇者少女を育てる~…