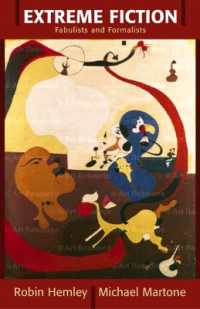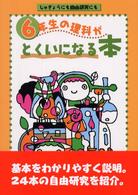目次
児童養護施設経験者調査の経緯と本書の概要
第1部 生育家族と施設生活(頼れない家族/桎梏としての家族―生育家族の状況;児童養護施設での生活)
第2部 学校から職業へ(施設の子どもと学校教育;高学歴達成を可能にした条件―大学等進学者の語りから;児童養護施設経験者の学校から職業への移行過程と職業生活)
第3部 差別とアイデンティティ(児童養護施設生活者/経験者のアイデンティティ問題;児童養護施設生活者/経験者の当事者活動への期待と現実)
家族依存社会、社会的排除と児童養護施設
著者等紹介
西田芳正[ニシダヨシマサ]
大阪府立大学人間社会学部准教授
妻木進吾[ツマキシンゴ]
大阪市立大学文学研究科特任講師
長瀬正子[ナガセマサコ]
常磐会短期大学講師
内田龍史[ウチダリュウシ]
大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター/部落解放・人権研究所研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
21
児童養護施設で育った子どもたちを社会的排除の視点から現状の問題点を考えた本です。12人の施設で生活し、今は施設を出て暮らしている人へのインタビューをもとに研究されています。施設で暮らすことは貧困と深く結びついている現状があり、また家族依存社会では限界があることが述べられています。社会的養護を受けている子どもたちへの社会的関心を高めていくことや施設に関わる専門職が自らの役割を認識することの大切さが述べられていたように思います。2015/03/03
maaaa
1
来春から児童養護施設で働きます。退所した若者のインタビューから様々なことが見えてきました。自分に何か措置されてきた子どもに何かプラスの影響を与えられるのだろうかとすごく不安にもなりました。ですが、職員への感謝の気持ちを述べる若者の言葉に救われもしました。学校への理解は必須ですね。特に中学、高校と上がるにつれて施設を知らない先生や同級生が増えることは改めて気づかされました。学校や社会に施設の役割と社会的養護下の子どもへの理解をどう求めるか、考えさせられました。加配のために施設の子を使うとは、怒りが溢れますね2015/10/23
てくてく
1
当事者としての元入所者へのインタビューとその分析。入所となったきっかけ、施設での生活、施設と学校の関係、その後(特に大学、短大、専門学校への進学などを達成した理由など)がまとめられている。親がいないことから、親による虐待、親の精神疾患、貧困などにより乳幼児段階あるいはそれよりは大きくなってから施設に入るようになった状況と、最近は多少変化したとはいえ高校後は進学よりも就職を求められることなど、負の連鎖を断つための手段が不十分であることが判明してどうしようも気が重くなる。2013/07/20
枕流だった人
0
市川市立図書館
よよ
0
こういう現実があるのかと思うと恐ろしい。なくしていきたいと切実に思った。でも、私には何もできない2011/05/19