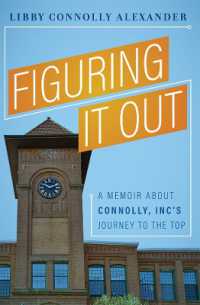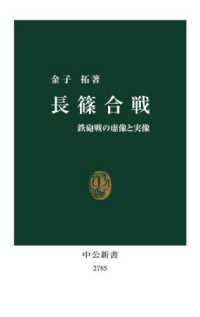内容説明
歴史と地図でたどるもうひとつの大阪案内。
目次
序論 絵図にみる被差別民の世界を歩く
エリア編(道頓堀;千日前;日本橋筋 ほか)
トピックス編(食肉文化と屠場;有隣小学校と徳風小学校;四ヵ所と七墓 ほか)
補論 “大大阪”と被差別民(インナーシティから“大大阪”へ;ディープ・サウス―釜ヶ崎と西浜・西成;アトラクティブ・ノース―本庄・長柄と舟場 ほか)
著者等紹介
吉村智博[ヨシムラトモヒロ]
1965年1月京都市生まれ。1988年3月立命館大学文学部史学科日本史学専攻卒業。2012年3月大阪市立大学博士(創造都市)。専攻は、近代都市部落史・近代寄せ場史。現在、大阪市立大学都市研究プラザ特別研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
大阪のきんちゃん2
12
図書館のいわゆる「人権」コーナーにあった小本。 街歩きの参考になるかと読みましたが、他とは違う切り口で大変興味深い本でした。 昭和初期、関東大震災後の東京を凌ぐ「大大阪」と称される巨大都市が形成される一方で、被差別民や貧民層が都市の縁辺部に組み入れられていく様を道頓堀・千日前・釜ヶ崎・新世界など市内名所?を通じて古地図を参照しながら歴史の隠れた部分を解説していくもの。 普通のガイドフックでは決して語られない内容は、街歩きをしていても別の視点を持たせてくれるものでしたが、肝腎の古地図の掲載が無いのは意図的?2025/11/07
浅香山三郎
11
ブックレット的な厚さの本なので、まう少し踏み込んでくれればなあと思ひながらも、大阪のまちの、周縁におかれた人びとにスポットをあてたものであり、その点で異色。大阪歴史博物館の方面委員制度100年の特別展(2018年12月3日迄開催)とも響き合ふ好著だと感じた。2018/10/14
chang_ume
4
近世大坂三郷=オールドシティの周縁に成立した、近代社会事業の集中エリア=「インナーシティ」について(釜ヶ崎、新世界、道頓堀、飛田、西浜など)。被差別民や生活困窮者の歴史的経緯を踏まえた生活史を活写しています。近年ブームの「まち歩き本」とは一線を画した内容。社会的マイノリティが排除・包摂の歴史の中で、いかにして「地域」を形作ったか。歓楽街・墓所・屠場・セツルメントなど、近代都市インフラが「そこにある」経緯への理解が、生活史への共感を伴って生まれました。巻末「“大大阪”と被差別民」からの読解がお勧めです。2017/08/02
狐狸窟彦兵衛
2
落語などに出てくる「貧乏長屋」や「遊郭」の変遷履歴が示されています。江戸時代から明治への「近代化」の中で、そうした「埒外の地」がどのように解体、再構成されていったかが「概観」されています。「かくれスポット」のタイトルには、「隠れた名所案内」の雰囲気がありますが、歴史のはざまの中で隠れてしまった大阪の歴史スポットが紹介されています。特に「貧民」「スラム」「どん底」などと「蔑まされ」「差別され」てきた人々の活動の変遷や歴史的意義が分かりやすく考察され、大阪の社会政策の意義などを新たな角度から見直せます。2015/08/14
miz_shiba
0
繰り返し書かれる 「アジア太平洋戦争」の表記にひっかかりました。著者の立場が分かるようです。2017/08/11