出版社内容情報
ミュンヘン近郊の町で、楽器店を営む両親と、障がいをもって生まれて来た妹と暮らす少年。彼の眼を通して、ヒトラーの台頭から、政権への反対者の逮捕、ユダヤ人差別・弾圧、障がい者の隔離をはじめとしたナチスの支配、そして第二次世界大戦とナチス・ドイツの敗北までを描いた物語。
戦争が終わり、廃墟となったミュンヘン郊外の町で、兵隊から復員してきた父親に少年は、「父さんはどうしてヒトラーに投票したの?」と最後に問いかけます。
前書きなど
この絵本の舞台になっているツォルンフェルトは架空の町です。ルディ少年とその家族の物語もフィクションですが、作者はヒトラー政権が成立した1933年から大戦が終わる1945年までの12年間にドイツで起きたことについてよく調べて書いていますので、こういう家族が実際にもいたと考えてくださって間違いないでしょう。
ヒトラー政権が成立した頃、世界はアメリカ合衆国で始まった恐慌のために経済が混乱していました。ドイツでは働ける年齢の男性の3分の1は仕事を失っていました。その中でヒトラーは「『ユダヤ人』のせいでこんな状態になっているのだ」と言い、「『ユダヤ人』がいないドイツ」をつくって、領土を東側(東欧やソ連)に広げればこの困難は解決する、そのために強い軍隊が必要で、軍備を妨げているヴェルサイユ体制を打ち破らなければならない、議会や民主主義は「強いドイツ」には必要ない……と主張しました。
政権をとって最初にしたことは、ヒトラーの政策に反対する人達を強制収容所に送ることでした。そして身近にいる「ユダヤ人」を攻撃し始めました。攻撃と言ってもすぐに捕まえたり殺したりするのではなく、まずは裁判官などの公けの職に就けなくする……ことから少しずつ始まりました。そして「ユダヤ人」とした人々の市民権を奪いました。子ども達は公立学校へ通えなくなりました。
また、ナチ・ドイツは成立直後から「新しいドイツに必要ない」「社会に負担になる」として、障がい者・精神的な病を持った人・「治らない」病気の人を施設で「安楽死」させる政策を展開していきました。この「安楽死」に関わった医師達やその方法が42年以降にアウシュヴィッツなどで実行される「ユダヤ人」虐殺に用いられていくことになりました。
ナチやヒトラーの考え方は過去のものになったのでしょうか? 経済がうまくいかなくなると「◯◯のせい」として社会の少数派を攻撃していくやり方は現在の世界でも頻繁に見られます。障がいを持つ人を「生きる価値がない」と19人の生命を奪った事件は私たちの社会で起きました。私達自身「私という人間の生きる意味はどこにあるのだろう?」と問いながら日々を暮らしているとも言えるかも知れません。社会や政治というものは私達の外にあるのではなくて、内側にもあるのでしょう。若い世代のみなさんが、これからのあなた自身と社会を考えていく時の材料の1つにこの本がなれば……と願っています。
著者プロフィール
ディディエ・デニンクス (ディディエ・デニンクス) (文)
1950年、パリ郊外サン=ドニ生まれ。1984年、『記憶のための殺人』でフランス推理小説大賞、ポール・ヴァイヤン・クーチュリエ賞を受賞。『未完の巨人人形』で813協会ロマン・ノワール大賞を、1987年に『プレイバック』でミステリー批評家大賞を受賞。
PEF (ピーイーエフ) (絵)
ペンネームの「ペフ」は、本名ピエール・エリー・フェリエ(Pierre Elie Ferrier)の頭文字から。1939年、フランスのソーヌ・エ・ロワール県サン・ジャン・デ・ヴィーニュ生まれ。文学を学んだのち、ジャーナリストとしてルポルタージュやBD(フランスのまんが)を手がけてる。
湯川 順夫 (ユカワ ノブオ) (翻訳)
1943年生まれ。翻訳家。
戦争ホーキの会 (センソウホーキノカイ) (翻訳)
2003年のイラク戦争と自衛隊派遣をきっかけに、憲法9条の条文タグをつけたミニホーキを作り、戦争放棄と平和を志向する思いを託して、人々に手渡す活動を続けてきた三多摩在住の女性グループ。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
keroppi
モリー
☆よいこ
♪みどりpiyopiyo♪
ぶんこ
-

- 電子書籍
- ハイスペ旦那には秘密がある 上【合冊版…
-
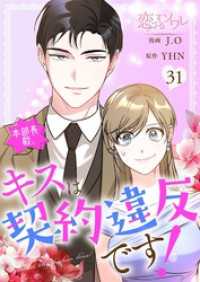
- 電子書籍
- 本部長殿、キスは契約違反です!【タテヨ…
-
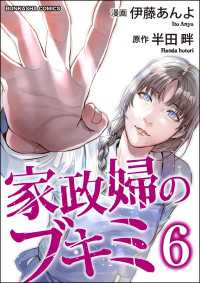
- 電子書籍
- 家政婦のブキミ (6) COMIC ヤ…
-

- 電子書籍
- オンラインセラピーの理論と実践 インタ…
-
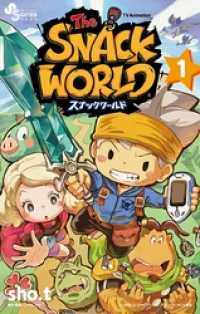
- 電子書籍
- TV Animation スナックワー…




