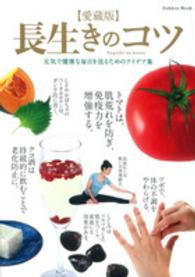内容説明
本書は「あー、そうだったのかの接辞学」である。英語を理解するには構文とともに語の仕組み(構造)と謂れ(語源)と語法を理解する必要がある。新しい視点で今まであまり焦点化されてこなかった接辞(接頭辞、接尾辞)に焦点を当て、その仕組みと謂れにメスを入れた。
目次
第1章 接辞の諸相(英語接辞の魅力;語の生産工場;なぜ接辞が語形成において大切か? ほか)
第2章 そうだったのかの接辞学(〔‐less〕とless;〔‐ful〕とfull;〔‐ful〕と〔‐ous〕 ほか)
第3章 接辞教育の必要性(「あー、そうだったのか」の積み上げ;WhyとBecauseの鎖;授業における接辞の活用 ほか)
著者等紹介
西川盛雄[ニシカワモリオ]
1943年神戸市生まれ。大阪大学大学院修了(英語学専攻)。ミネソタ大学(フルブライト奨学生)、ランカスター大学(国際ロータリー財団奨学生)大学院に留学。熊本大学客員/名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
剛田剛
1
どんな言葉もその形、その意味になるまでの過程が存在するし、最終的には音素にまで遡ることができる。おそらく言葉を獲得し、言語によって世界の認識を形成し始めた時がヒトの誕生した瞬間なのだろう。サルの吠え声とヒトの言葉の境目はいつ、どこに存在したのか。英語は辺境の・足の短い言語ではあるが、その成り立ちを学習することは言語について学ぶための第一歩になるだろう。(母語たる日本語は学問として対象化することが難しい)2022/10/07
dobrydenkrtek
0
知っている人には当たり前のことが書かれているのかもしれないが、僕にはとても参考になった。この本は英語についてがメインだが、当然ほかの言語にもその視点を開かせてくれ、新しい読書リストを作れたのがありがたい。一読するだけでも、へぇーという話が多く、自分の英語力の底上げになった気がする(だけかもしれないが)。2017/05/11
たく
0
☆☆☆2015/09/24