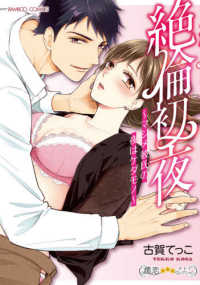内容説明
「言語表現」と推論が「個人概念a」と「個人概念b」の間に交わされることによって言語コミュニケーションが成立すると捉えるモデルを提案する。「言語表現」は形式と意味のペアによって、「個人概念」は概念によって構成される。話し手は、自身の概念を基に「言語表現」を産出(“言語化”)し、聞き手はその「言語表現」の意味を自身の「個人概念」に取り込む(“概念化”)。そのやり取りによって自然言語の秩序が成り立つ。
目次
第1章 言語コミュニケーションのモデル(言語コミュニケーションにおける“概念”と“意味”の相関;「相関モデル」対コードモデル/推論モデル ほか)
第2章 “言語化”とは(文法概念の位置づけ;“言語化”における概念的なまとまり ほか)
第3章 “概念化”とは(言語処理のモデルvs.言語コミュニケーションのモデル;“概念化”という“理解”の幅 ほか)
第4章 言語化と概念化の非対称性(言語産出の言語理解の一般的非対称性;「相関モデル」における非対称性 ほか)
第5章 同時通訳はなぜ可能か(手話通訳は同時通訳;同時通訳の特殊性と一般性)
著者等紹介
船山仲他[フナヤマチュウタ]
1950年大阪府生まれ。1974年大阪外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業、1976年京都大学大学院文学研究科修士課程言語学専攻修了、1979年同博士課程単位取得満期退学。京都工芸繊維大学助教授、大阪府立大学教授、神戸市外国語大学教授、学長を経て、神戸市外国語大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。