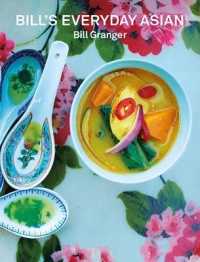内容説明
「近所を散歩したとき、私はついに、窓のある書店を見つけたのだ。店内には一匹の猫がいる」―二十五年前、二十八歳のわたしは、まさか、自分が書店の店主になるとは想像だにしなかったはずだ。言葉と深く向かい合い、読み、書き、ともに生きる。作家・柳美里の血と肉になってきた書物とその心の遍歴―極上のエッセイ本に、「古都鎌倉、あるいは生と死の交錯する場所」「カトリックの洗礼式」「谷崎潤一郎」「阿佐田哲也」など五〇ページの新たなエッセイを加え、装いも美しく登場。
目次
1(韓の国にて;不自由な言葉;「“恨”を越える」ということ ほか)
2 窓のある書店から(猫の巻;海の巻;日記の巻 ほか)
3(地下鉄の図書館;天井の“染み”と短篇集;七十九頁行き ほか)
著者等紹介
柳美里[ユウミリ]
1968(昭和43)年、茨城県生れ。高校中退後、「東京キッドブラザース」を経て、1988年、演劇ユニット「青春五月党」を結成。1993(平成5)年、『魚の祭』で岸田國士戯曲賞、1996年、『フルハウス』で野間文芸新人賞、泉鏡花文学賞、1997年、『家族シネマ』で芥川賞、1999年、『ゴールドラッシュ』で木山捷平文学賞、2020(令和2)年、『JR上野駅公園口』で全米図書賞を受賞。2018年4月から南相馬でブックカフェ「フルハウス」を営む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
*
15
【読書という行為は、書物のなかに眠っている〈知〉と〈血〉を揺り起こすことである。"(P.5)】本を読む時、苦心するのは「目を合わせる」作業。著者と読者とでは視点が全く違うから。よく「巨人の肩に乗る」というが、安易な気持ちで臨めば振り落とされる。特にこの本は、著者が作家を見つめる視線、言葉に向ける姿勢の安易なトレースを許さない▼フラットな感情では読み切れない、逃げ切れないし、 己の文学的教養の低さも突き付けられる。でも、反射的な共感よりも大事なものがある、それを探せと言われているような気がした。2022/09/05
Cinejazz
14
〝 私はかねがね書店に窓がないのは、どうしてだろうかと、不思議でならなかった...近所を散歩したとき、私はついに、窓のある書店を見つけたのだ。店内には一匹の猫がいる 〟〝2018年4月、私は福島県南相馬市小高区に「フルハウス」という書店を開いた〟・・・芥川賞作家<森美里さん>の血と肉となってきた書物の世界を、縦横無尽に読み砕いた心のエッセイ集。〝 こどもの頃に私が心を許せたのは、死者たち―物語を書いて死んでいったひとたちでけだった。E.A.ポ-、小泉八雲、中原中也、そして太宰治― 〟2023/08/14
ゆみにてぃー。
14
元は1996年に出版されたものを再編した本。著者柳美里さんが在日韓国人だったことに驚き。はじめは読み慣れないエッセイ感があるが途中から、「言葉」のもつ意味を本当に使いこなして本を描く難しさのようなものを感じた。近年ではご自身で南相馬市に書店を開いている。柳美里さんファンにはいい本なのでは。2022/11/02
たっきー
8
1996年初出、1999年文庫化されたものを再編されたもの。骨のあるエッセイ集で、何日かかけて読んでいった。言葉に重みがある。2021/10/29
qoop
5
著者が生きる上で/書く上で糧として来た書籍や作家を扱ったエッセイ集。その本を読むことで著者が人生を今に繋いで来たという重みを感じさせる内容で、本と読書に対する飢餓感のようなものが各ページに満ちていて、数多ある本に関するエッセイの類とは一線を画している。時系列で書かれている訳ではないけれど、ある意味で読書体験で綴る自伝のような読み応え。更にいうと、それが今につながって福島での書店経営になっているのかと思えば、書店主となった著者がどんな本を売るのかと興味が広がっていく。2024/07/01