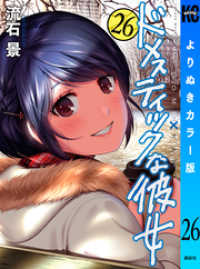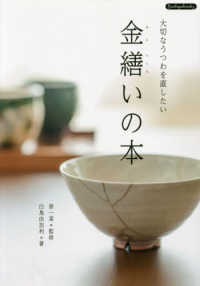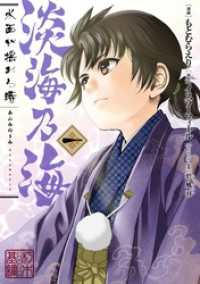内容説明
いかなる方向に臨めば日本が文化的小児病から脱することができるのか、そしてその果てに日本文明の成熟をすら望みうるのか(「西欧の自己懐疑と日本の自己放棄」より)―保守的自由主義の源流、エドマンド・バーク、「大衆」に関して、それを「奇怪」なる存在と捉えていたキルケゴール、民主主義批判をしたニーチェ…など十五人の思想家たちの言説を、私たちが今を生き抜くための精神的な糧にしようとする画期的な書、待望の文庫化。
目次
西欧の自己懐疑と日本の自己放棄―序章
保守的自由主義の源流―エドマンド・バーク
大衆批判の原点―セーレン・キルケゴール
多数者への抗議―アレクシス・ド・トックヴィル
近代に突き刺さった棘―フリードリッヒ・ニーチェ
進歩への悲観―ヤーコブ・ブルクハルト
群衆への闘い―ギュスターヴ・ル・ボン
諧謔による正統の擁護―ギルバート・チェスタトン
文明という名の死―オズヴァルト・シュペングラー
文化的小児病への恐怖―ヨハン・ホイジンガ〔ほか〕
著者等紹介
西部邁[ニシベススム]
1939年、北海道生まれ。東京大学経済学部卒。横浜国立大学教授、東京大学教授を経て、88年3月に辞任。83年、『経済倫理学序説』で吉野作造賞を、84年、『生まじめな戯れ』でサントリー学芸賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
良本を読もう本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
12
日本を代表する保守主義者として知られた西部邁自身による、保守思想史のスケッチ。いや、あくまで同時代の日本の状況を保守思想の巨星たちの言葉を頼りに批判することを意識している点で、彼の終生重視した概念である歴史的理性を展開するための内的対話集とも言えるだろう。バークやオークショットだけでなく、キルケゴールの広告批判と日本の広告社会を対峙させ、ホイジンガやブルクハルトの歴史哲学から保守主義につながる洞察を汲み取るあたり視点の独自性も光っている。保守思想史としても、また独自の保守思想論としても気骨のある傑作である2018/08/07
とうゆ
11
△保守、伝統、慣習。現代日本ではこれらの言葉は否定的な意味を持つ。保守は発展的な改革を妨げ、伝統や慣習は個人の自由を阻害する。伝統などは社会から切り離し過去の歴史として適度に保護するのがよく、もはや日常では必要ないのだという考えが多いのではないだろうか。しかし、少数ながら逆の考え方、伝統や慣習を重視する人達もおり、本書ではその数少ない保守思想家たちが紹介されている。一人当たりのページ数が少ないのは難点だが、その分多くの人物を知ることができたのでよしとする。2014/07/18
kanaoka 58
7
人は言語により世界を認識する。歴史と伝統は、先人から引き継がれた知恵であり、世界に秩序をもたらす。伝統の放棄、価値の相対化は、世界と人にカオスをもたらす。 近代社会が生み出した、合理主義、科学主義、個人主義、自由主義は、大衆を煽動し、個人の内面の混乱を、社会に拡散させていく。革新は、革新がゆえ、これを抑制する仕組みをもたない。保守は現状維持、過去回帰ではなく、変化するものと、伝統との平衡であり、革新に対する抑制機能である。 2017/08/20
ドクターK(仮)
6
西欧近代において、保守論と大衆論がその流れの中心にあったと著者は言う。だからこそ、保守という考え方が疎んじられ(あるいは曲解され)、大衆に半ば支配された現代の日本に、本書は必要とされていると私は確信している。2014/03/21
スーさん
5
15人の保守思想家と向き合うことで、戦後の日本社会に対する批判を試みた一冊である。本書は平成8年に出版されたものを文庫化したものだ。しかし驚くべきか悲しむべきか、本書でなされている批判は現在にもピタリと当てはまっている。つまり我が国のここ十数年間の歩みは、保守主義からは対極に位置する小泉元総理が典型であるが、改革に次ぐ改革の政治だったのだ。今こそ改革派に対して「懐疑」し、国家を「有機体」として受け止め、「漸進」的な変革を希求する保守主義と真剣に向き合うべきではないのか。その知的営みの一助となる好著である。2012/06/26