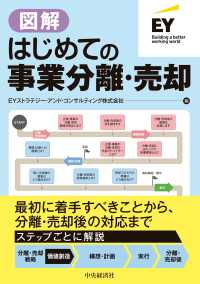内容説明
個という存在の確かさや愛おしさを、おおらかな息づかいでうたいつづけた草野心平。本書では、蛙の詩人としても知られる著者の代表作「ごびらっふの独白」をはじめ、“易しくて、優しい”言葉で綴られた一〇六篇を精選。文庫オリジナル版。
目次
1 蛙(定本 蛙;第百階級;第四の蛙)
2 マンモスの牙ほか(明日は天気だ;絶景;大白道 ほか)
3 年次詩集(凹凸;全天;植物も動物 ほか)
著者等紹介
草野心平[クサノシンペイ]
1903年、福島県上小川村(現・いわき市)生まれ。1919年、磐城中学(現・福島県立磐城高等学校)を中退したのち上京。1920年、慶應義塾普通部に編入するも同年中退し、1921年、中国の嶺南大学(現・中山大学)に進学する。亡き兄民平の詩稿に影響を受け詩作を開始し、1923年、民平と自己の詩をおさめた『廃園の喇叭』をガリ版刷りで自費出版。1928年、初の活版刷り詩集『第百階級』を刊行。1935年、中原中也らと詩誌『歴程』を創刊(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新地学@児童書病発動中
140
言葉はもどかしいものだ。特に散文はもどかしい。胸の中に伝えたい想いがあふれていても、整った散文でそれを伝えようとすると、その想いの熱がいつの間にか冷えてしまう。だから草野心平は詩を書いたのだろう。胸の中の熱い想いをそのままつかみ取って、書きなぐったような詩を書き続けた。そういった詩を読んでいると、こちらの胸の中まで熱くなる。この詩人の場合は、言葉というより胸の中そのものを引きちぎって、詩にしたような所がある。だから読んでいると、身震いするような感動を覚えるのだ。(コメント欄へ続きます)2016/02/01
クプクプ
72
草野心平は阿武隈山脈のそばで育ち、自然が好きで特にカエルが好きだったようです。カエルやオタマジャクシの詩を擬音を大胆に使って描きました。池の上の木の枝に卵を産むモリアオガエルの詩もあって、実際にモリアオガエルの保護活動もしたそうです。擬音を使う作風は宮沢賢治の世界に近いものを感じました。また、高村光太郎とも親交が深かったようです。草野心平は85才まで生きられて幸せだったことでしょう。2022/11/04
まさ
25
ケルルン クック(春のうた)は収録されていませんが、蛙のいろいろな鳴き声が聴こえてきました。近くの田んぼからとこの本から。オノマトペが心地よい。――るるり。りりり。――2020/07/22
ハナコ
22
蛙が好きなわけではないのですが、なぜだかひかれて。図書館本なので早めに読んだけれど、詩集というのは、季節ごと、心の動くごとに読みたいですね。 「天は。螺鈿の青ガラス。」(夜の天) 美しく、せつない。 でも特に印象的なのはやはり、昔読んだことのある「どうしてだろう。うれしいんだのに。どうして。なんか。かなしいんだろ。」(おたまじゃくしたち四五匹)かな。2015/08/24
来未
14
読書をするようになり小説をメインで読んできたが初めて詩集を呼んだ。草野心平さんの蛙を使っての詩。自分が思ってた詩とは何か違う感じがした。本として活字で表現されている中、文学的な印象よりもビジュアル的な?クリエイティブの要素を感じる作品もあった。「月の出と蛙」「生殖Ⅰ」「Nocturne.Moon and Frogs.」そして、ん?何これ?でもなんかわかるぅ…と思った「冬眠」。詩なのにタイポグラフィみたいな印象もあって読んでいて楽しくもあった。読書を続けているといろんな本と出会うもんだと改めて思った一冊。2021/12/03