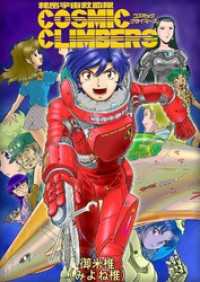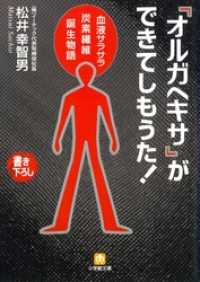出版社内容情報
《内容》 機器の開発で測定法がより簡便となり、臨床や健診に積極的に利用されるようになってきた脈波速度に関する基礎・臨床・予後・臨床治療への応用をわかりやすく解説した入門書。
《目次》
序文 小澤利男,増田善昭
脈波速度に関連する用語解説
1.脈波の基礎
圧波と血流波:生理学的考察 入内島十郎
1. 圧波と血流波の操作定義
2. Moens-Kortewegの式の誘導
3. 動脈系の体積の推定
4. 脈波と流速
圧波(脈波)の波形 増田善昭
1. 記録
2. 正常波形の名称
3. 圧波の成因
4. 正常脈波の伝播に伴う波形変化
5. 伝播に伴う異常波形
6. 大動脈弁および左室流出路異常による波形変化
脈波速度測定法 山科 章
1. 脈波速度測定の原理と歴史
2. PWVの測定法
(1)頸動脈―大腿動脈(carotid-femoral PWV ; cf PWV)法
(2)上腕動脈―足首動脈間(brachial-ankle PWV ; baPWV)法
3. baPWV法の精度と再現性
4. PWVの基準値
5. PWV計測の問題点
脈波速度に関係する因子 庄司哲雄,木本栄司,篠原加代,横山久代,西沢良記
1. PWVを決定する要因
2. PWV変化の背後にある動脈壁の病理組織学的変化
3. 加齢とPWV
4. 血圧とPWV
5. 性別とPWV
6. 食生活とPWV
7. 運動とPWV
8. 糖尿病とPWV
9. 腎不全とPWV
10. 種々の因子が与えるPWVへの影響は全身の動脈に一様か
11. PWV改善を目指したインターベンションの可能性
2.脈波速度の臨床
高血圧 小澤利男
1. 加齢に伴う血圧値の意義
2. 脈波速度と高血圧の関係
3. 高血圧におけるPWVの臨床的意義
糖尿病 保阪大也,大村栄治,河津捷二
1. 糖尿病と動脈硬化
2. 糖尿病とPWV
3. 糖尿病とABI
高脂血症・肥満 今井康雄,河津捷二
1. 高脂血症とPWV
(1)動物実験
(2)臨床
(3)高脂血症治療の影響
2. 肥満とPWV
虚血性心疾患 戸田源二,矢野捷介
1. 測定方法
2. 大動脈硬化度と虚血性心疾患における脈波速度
3. 冠動脈造影施行症例を対象としたPWVに関する研究結果
脳血管障害 藤代健太郎
1. 脳血管障害例の大動脈壁膨張性は低下し大動脈脈波速度は高値を示す
2. 脳血管障害では頸動脈硬化も進展している
3. 病理所見からPWV値が8m/secを超えると脳動脈硬化や冠動脈硬化が出現する
4. PWV値が8.5m/sec以上を異常値とすると虚血性心疾患に比較して脳血管障害例で異常値の率が高い
腎不全 西田英一,小川哲也,末永多恵子,二瓶 宏
1. 慢性腎炎・保存期腎不全患者の脈波速度
2. 慢性血液透析患者の脈波速度
3. 血液透析患者の脈波速度の測定時期
4. 脈波速度と腎不全患者の予後
閉塞性動脈硬化 正木久男
1. 閉塞性動脈硬化症と脈波速度
(1)他の動脈硬化性疾患とのPWVの比較
(2)ASOの患肢と有意な狭窄病変のない対側肢とのPWVの比較
(3)ABIとPWVの関係
(4)動脈硬化危険因子とPWVの関係
2. PWVに影響する因子
3. 各種治療前後のPWVの変化
(1)PTA,stent挿入
(2)運動療法
(3)バイパス
4. 予後とPWV
高齢者 西永正典,小澤利男
1. 脈波速度に関与する諸因子
(1)年齢と血圧
(2)その他の因子:心拍数,BMIなど
2. 心血管疾患との関係(予知因子)
3. 痴呆,認知機能との関係
ホルモン 岩井愛雄,橋本正良,秋田穂束
1. エストロゲンの抗動脈硬化作用
(1)脂質代謝に対する作用
(2)動脈壁に対する直接作用
2. Arterial Stiffness増加の機序
3. 女性の更年期とPWV
4. ERTと血圧
5. ERT/HRTとPWV
血管内皮機能検査 秋下雅弘,橋本正良,鳥羽研二
1. 血管内皮機能検査の原理,方法,特徴
2. 血管内皮機能の病態・治療による変化
3. 血管内皮機能検査とPWVとの関係
3.予後
動脈硬化度の評価と危険因子
非侵襲的動脈硬化診断法を中心に 都島基夫
1. 「動脈硬化症」の臨床大系化と動脈硬化の評価
2. 危険因子の評価
3. 非侵襲動脈硬化診断の生理機能検査
(1)脈波伝播速度(PWV)
a)PWVと影響する因子・血管壁性状
b)PWVと危険因子
c)PWVの予後
(2)定量的脳頸動脈系血流測定装置(QFM)
4. 非侵襲動脈硬化診断の画像診断
(1)Bモード超音波断層法
(2)X線CT
(3)磁気共鳴画像(MRI,MRA)
健診ならびに人間ドックにおける意義 山科 章,冨山博史
1. 動脈硬化疾患と脈波速度
2. 心血管疾患発症リスクと脈波速度
3. 介入治療と脈波速度
4. 脈波速度を健診に導入するには
5. 健診における脈波速度基準値
6. 健診における脈波速度の利用
7. PWVの限界と課題
4.脈波速度の臨床治療への応用
非薬物治療:運動,食事,食塩制限,禁煙など 松田光生
1. 運動
2. 食事,食塩制限
3. 禁煙
薬物療法 苅尾七臣,星出陽子
1. 降圧療法時のPWVモニターの臨床的意義
2. レニンアンギオテンシン系と遺伝的素因
3. 急性効果
4. ACE阻害薬とARB
5. スピロノラクトン
6. カルシウム拮抗薬
7. α遮断薬・β遮断薬
8. 利尿薬
9. 亜硝酸薬
10. その他
内容説明
本書は、臨床家に今までなじみの薄かった「脈波速度」のいわば入門解説書である。脈波速度は、血圧のように一定の共通の数値が広く認知されるまでには至っていない。しかし、測定法が一定であれば、その値の基準値も自ずと定まってくる。その様々な変動を検討することは、これからの保健と医療の面で大きな貢献をすることになるだろう。
目次
1 脈波の基礎(圧波と血流波:生理学的考察;圧波(脈波)の波形
脈拍速度測定法
脈拍速度に関する因子)
2 脈波速度の臨床(高血圧;糖尿病;高脂血症・肥満;虚血性心疾患;脳血管障害;腎不全;閉塞性動脈硬化;高齢者;ホルモン;血管内皮機能検査)
3 予後(動脈硬化度の評価と危険因子―非侵襲的動脈硬化診断法を中心に;健診ならびに人間ドックにおける意義)
4 脈波速度の臨床治療への応用(非薬物治療:運動、食事、食塩制限、禁煙など;薬物療法)
著者等紹介
小沢利男[オザワトシオ]
東京都老人医療センター名誉院長
増田善昭[マスダヨシアキ]
千葉大学グランドフェロー
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。