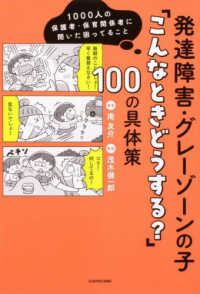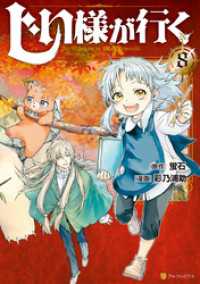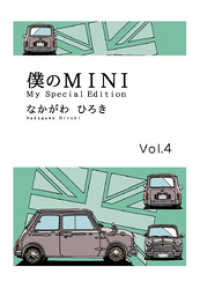内容説明
原因疾患が多すぎる…病歴がとれない…意識障害の怖さ・不安を克服。致死的疾患を見落とさない系統的な初期診療が身につく。Primary、Secondary、Tertiary Surveyの流れに沿って、各段階でやるべきことをマスター。「まずい!意識に障害、試して酸素」の語呂合わせで鑑別すべき原因を覚える。現場の機微と、ベテランの経験が満載のケーススタディとコーマ・ルールで実践力をアップ。最近の知見や先進医療も紹介。一歩進んだ知識も身につく。
目次
第1章 総論 原因疾患を見落とさないために!系統的な初期診療の進め方(意識障害とは;ACECとは―意識障害初期診療の標準化をめざして;Primary Survey まず何を行うべきか―神経系にかかわる生理学的異常と蘇生 ほか)
第2章 ケーススタディ 原因疾患への対応とコーマ・ルール(薬物・毒物中毒;脳炎・髄膜炎、脳症;低血糖・高血糖 ほか)
第3章 Special Lecture さらに視野を広げるために!(PCECの目的と実際;敗血症性脳症の最近の知見;ICUせん妄に関する最近の知見 ほか)
著者等紹介
堤晴彦[ツツミハルヒコ]
埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター教授。1977年東京大学医学部卒業、脳に興味があって脳神経外科学教室に入局。その後、派遣先の救急病院で、多くの重症患者を前にして、何もできない自分に呆然と立ちすくむ。大学の医局を辞め、大阪府立病院救急医療専門診療科に弟子入り。その後、1981年東京大学救急部の創設、1985年東京都立墨東病院の救命救急センターの新設に参画。1995年から現在の職場に
輿水健治[コシミズケンジ]
埼玉医科大学総合医療センター救急科(ER)教授。1981年桃京医科大学卒業。当時の東京医科大学麻酔学教室では、大学院在学中から内科、外科、放射線科などさまざまな診療科の研修をしていました。この時期に総合診療の基礎を築くことができ、自身の救急医療の原点だと思います。その後戸田中央総合病院へ出向、1995年救急部を設立し救急専従の第1歩でしたが、今にして思えばER型救急でした。堤教授に誘われて、大学病院でER型救急医療システム作りと若手育成のため、2006年現在の地へ赴任しました
中田一之[ナカタカズユキ]
埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター講師。1988年帝京大学卒業、帝京大学市原病院(現・ちば総合医療センター)で内科学を研修。1990年埼玉医科大学第二内科で心臓カテーテルを習得。1998年埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター・堤晴彦教授の門下生となり、現在に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。