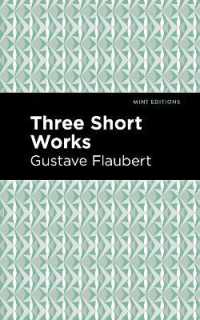内容説明
読本という新たなジャンルを切り開いた先駆者、都賀庭鐘についての初めての研究書。江戸時代中期の読本作者・都賀庭鐘(1718~1794)は、白話小説を含む、あらゆる分野の漢籍を読みこなし、そこから得た新奇な素材を日本の歴史譚や伝説、軍記と融合させ、数々の翻案小説を著した。その斬新な発想と手法は、上田秋成や曲亭馬琴など後世の読本作者に多大な影響を与えたが、広範な和漢の文献を駆使した庭鐘の作品は、創作技法も難解で、いまだ明らかにされていない部分も多い。本書は、庭鐘の自筆読書筆記『過目抄』を最大限に活用し、庭鐘の読書の実態や学問の内実を詳細に考察、作品の典拠や生成過程、創作意図、創作方法などを解明する。
目次
第1部 都賀庭鐘読本の典拠研究(『英草紙』第六篇「三人の妓女趣を異にして各名を成す話」典拠考;『莠句冊』第五篇「絶間池の演義強頸の勇衣子の智ありし話」典拠考;『通俗医王耆婆伝』典拠考;『義経磐石伝』典拠考;都賀庭鐘読本における『水滸伝』の受容)
第2部 都賀庭鐘読本の新解釈(『繁野話』第三篇「紀の関守が霊弓一旦白鳥に化する話」新論;『繁野話』第八篇「江口の遊女薄情を憤りて珠玉を沈る話」新論;『垣根草』新論)
第3部 都賀庭鐘の読書と習作(都賀庭鐘の読書筆記『過目抄』とその読本創作;都賀庭鐘の白話運用―『通俗医王耆婆伝』を中心に)
著者等紹介
劉菲菲[リュウフェイフェイ]
1983年中国新疆生まれ。四川師範大学文学院、和歌山大学大学院教育学研究科修士課程、名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程を経て、2016年に名古屋大学で博士(文学)学位取得。専攻は日本近世文学。現在、中国の揚州大学外国語学院准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
紅林 健志