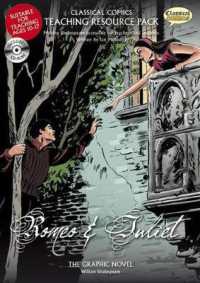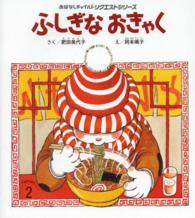内容説明
挿絵分析による「解釈」という画期的研究。仮名草子『大坂物語』の享受史を挿絵から解明。『大坂物語』・『嶋原記』において改版の度に挿絵を差し替えるのはなぜなのか?複数の挿絵に「型(モチーフや構図)の継承」が見られるか否かの美術史学研究の学際的手法を取り入れて分析し、当時の書肆が作品に対する世論を感知して反映した結果であると考察。同一作品でも江戸版と上方版では挿絵に異なる傾向があり、さらに時期によって内容が変化することが明らかにされた。
目次
序章 挿絵解釈の研究意義
第1章 『大坂物語』の挿絵分類
第2章 上方版『大坂物語』の挿絵―寛永無刊記版と正保三年版を中心に
第3章 江戸版『大坂物語』の形成とその周辺―挿絵・「頸帳」からみる成立順序に関する考察
第4章 寛文年間刊行の『大坂物語』の挿絵・「頸帳」比較―全盛期の江戸版『大坂物語』と上方(京)版の『大坂物語』
第5章 延宝頃版『大坂物語』と寛文十三年山本版『嶋原記』の挿絵―挿絵と「頸帳」の事実確認
第6章 西村屋版『大坂物語』の「頸帳」と本文と挿絵
第7章 『嶋原記』挿絵考―上方版『嶋原記』と江戸版『嶋原記』の相違にみる『大坂物語』との関連性
第8章 服部九兵衛版『天草物語』系統の挿絵の変遷―萬屋彦太郎版『嶋原記』と岩瀬文庫本『嶋原記』をめぐって
終章
著者等紹介
位田絵美[インデンエミ]
三重県生まれ。名古屋大学大学院文学研究科博士課程前期修了。名古屋大学大学院国際開発研究科博士課程修了。北九州工業高等専門学校准教授を経て、現職。近畿大学産業理工学部教養・基礎教育部門准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。