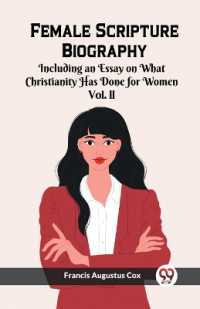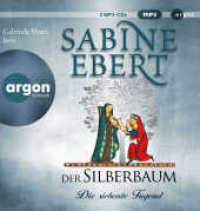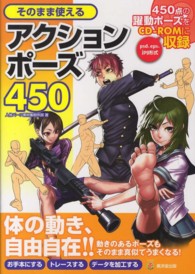内容説明
1982年以来、著者が提唱し続けた「構成意味論Constructive Semantics」研究の集大成。長年のフィールドワークで発見した「図式語彙」を手掛かりに、佐渡に伝わる昔話「鶴女房」の解釈学を展開。作品の解釈学的基底を拓き示し、話者たちの有声/無声の語りを浮かび上がらせていく。社会が混迷を極め、既存パラダイムが必ずしも通用しなくなった昨今、語彙学に基づく「人間活動」全般の“基底的事実学”構築の可能性を示唆する本著の試みは、注目に値する。
目次
第1章 作品のテクスト解釈の方法と手順(解釈に見る配意;昔話「鶴女房」;解釈における述語への注目と項の据え立て ほか)
第2章 テクスト分析―狭文脈に存在の類・種連関を読む(作り手や語り手たちの意識の構え―図式語彙の網状組織;活動空間から見た登場人物の類・種連関―狭文脈の構成;活動空間から見た作中事物の存在連関 ほか)
第3章 テクスト分析―広文脈に無声の思想を読む(文脈とは何か?;文脈の記述;広文脈の構成と発声なき主張 ほか)
著者等紹介
野林正路[ノバヤシマサミチ]
1932年台湾旧「台北州」基隆市生まれ。1968年東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程修了。法政大学助教授、ハワイ大学客員講師、茨城大学教授、北京大学客員教授、麗澤大学教授、中国首都師範大学客員教授などを経験。茨城大学名誉教授、文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。