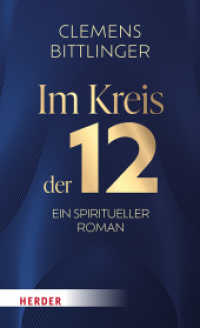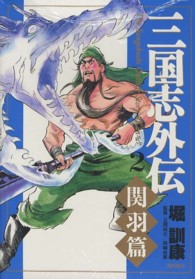出版社内容情報
表記研究では未開拓の俳諧を調査し、振り仮名、特殊な用字、音象徴語、定家仮名遣、節用集との比較等、近世初期の表記の実態を論究。多様な表記史の資料中、未開拓の俳諧を文字領域として、漢字表記と振り仮名の関係や機能、特殊な用字、音象徴語、定家仮名遣の使用、節用集との比較等、近世初期、蕉風成立以前の俳諧集の表記の実態を明らかにした。今後の表記研究の便宜に資することを期待して、「10俳諧集における振り仮名を付す語」他を資料編として収載。
序文 乾 善彦
序 章 本書の目的と構成
1 目的と方法
2 構成と概要
第一章 振り仮名が付される漢字表記語と表記形態
導 言
第一節 『紅梅千句』における振り仮名
はじめに
一 漢字と振り仮名の数量的側面
二 振り仮名付漢字表記語と俳諧作法書との関係
三 振り仮名を付す条件
おわりに
第二節 『軒端の独活』と『江戸宮笥』の表記
はじめに
一 漢字の数量的側面からの考察
二 『軒端の独活』を中心にした表記の特徴
三 『江戸宮笥』の振り仮名
おわりに
第三節 『正章千句』の振り仮名
はじめに
一 振り仮名の分類
二 『紅梅千句』との比較を通して
おわりに
第四節 『宗因七百韻』と『七百五十韻』の表記
―振り仮名の機能と表記形態の特徴―
はじめに
一 『宗因七百韻』の振り仮名を中心にして
二 『七百五十韻』の漢字使用の実態
おわりに
結 語
第二章 近世初期俳諧の用字・用語考証
導 言
第一節 『江戸八百韻』に見える「やさし」の用法
―「婀娜(ヤサシ)」「艶(ヤサ)し」について―
はじめに
一 「婀娜(ヤサシ)」について
二 「艶(ヤサ)しき」について
三 「やさし」に対応する他の漢字の用法
四 仮名書き「やさし」の用法
おわりに
第二節 『當流籠抜』における「悶(イキ)る」について
はじめに
一 古辞書類における「悶」と「いきる」
二 「悶」字の用法
三 仮名書き「もだゆ」の用法
四 「いきる」の用例
五 「煩」と振り仮名の関係
おわりに
第三節 『江戸八百韻』に見える「?」の訓みについて
はじめに
一 辞書類での「?」と「アツカフ(ヒ)」
二 「?」の用例とヨミ
三 「?」について
四 「扱」について
おわりに
第四節 『西鶴五百韻』の用字
―熟字訓と当て字―
はじめに
一 「日外」について
二 「性躰」について
三 「上夫」について
おわりに
第五節 『紅梅千句』に見える「ふためく」について
はじめに
一 古辞書類での「ふためく」と「はためく」
二 ふためくの用法
三 はためくの用法
四 「ふためく」と「はためく」の比較
五 「ふたふた」と「はたはた」
おわりに
第六節 近世初期俳諧における音象徴語
はじめに
一 音象徴語の数量的側面
二 音象徴語の分類と意味用法
三 漢語の音象徴語
おわりに
結 語
第三章 仮名遣いから見た近世初期俳諧集
―語頭に「お(オ)」「を(ヲ)」が付く語について―
導 言
第一節 本文中の語頭に「お」「を」が付く仮名表記語
―定家仮名遣を通して―
はじめに
一 仮名表記語と定家仮名遣の関係
二 定家仮名遣に準じると見做した語
三 定家仮名遣と一致しない語
おわりに
第二節 振り仮名の語頭の「オ」「ヲ」の仮名遣い
はじめに
一 同語における振り仮名と仮名表記の語頭の仮名遣いが一致する語
二 振り仮名と仮名表記の仮名遣いが異なる語
三 振り仮名の仮名遣いと定家仮名遣・節用集との関係
おわりに
結 語
終 章 本書の結論と今後の課題
あとがき
資料編
【資料一】 『紅梅千句』の振り仮名を付す語と俳諧作法書との関係
【資料二】 『紅梅千句』の振り仮名を付す語と条件との関係
【資料三】 10俳諧集における振り仮名を付す語
索引
田中巳榮子[タナカミエコ]
著・文・その他
内容説明
振り仮名は、なぜ付されたのか―多様な表記史の資料中、未開拓の俳諧を文字領域として、漢字表記と振り仮名の関係や機能、特殊な用字、音象徴語、定家仮名遣の使用、節用集との比較等、近世初期、蕉風成立以前の俳諧集の表記の実態を明らかにした。今後の表記研究の便宜に資することを期待して、「10俳諧集における振り仮名を付す語」他を資料編として収載。
目次
序章 本書の目的と構成
第1章 振り仮名が付される漢字表記語と表記形態(『紅梅千句』における振り仮名;『軒端の独活』と『江戸宮笥』の表記 ほか)
第2章 近世初期俳諧の用字・用語考証(『江戸八百韻』に見える「やさし」の用法―「婀娜」「艶し」について;『當流籠抜』における「悶る」について ほか)
第3章 仮名遣いから見た近世初期俳諧集―語頭に「お(オ)」「を(ヲ)」が付く語について(本文中の語頭に「お」「を」が付く仮名表記語―定家仮名遣を通して;振り仮名の語頭の「オ」「ヲ」の仮名遣い)
終章 本書の結論と今後の課題
著者等紹介
田中巳榮子[タナカミエコ]
1941年大阪府に生れる。2013年関西大学大学院博士後期課程修了。博士(文学)。関西大学東西学術研究所非常勤研究員。専攻、近世表記史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。