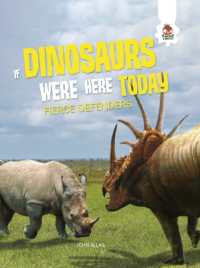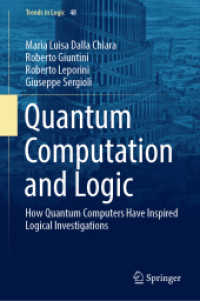出版社内容情報
助動詞、敬語の用法を考察する語法篇、源氏物語の清濁と用語を扱う語彙篇、ポルトガル語資料から日本語に迫るキリシタン資料篇の三篇本書は、中古語中世語に関する著者のこれまでの研究をまとめた論文集であり、語法篇・語彙篇・キリシタン資料篇の三篇から成る。
語法篇では、推定伝聞の助動詞「なり」の承接と意味、「今夜」「夜前」の指す時間と助動詞「つ」「き」の用法、「給ふる」「侍り」の用法の差、「申す」「聞こえさす」「聞こゆ」の敬意の差、受益敬語「てたぶ」の成立、形容詞「遅し」の用法について論じる。
語彙篇では、『首書源氏物語』に見られる「ときとき」「ときどき」の使い分け、一般に濁って読まれる「調ず」「らでん(螺鈿)」が清音であったこと、「けそん」が「家損」ではなく「気損」であること、「ウソ」「ハッケヨイ」の語源について論じる。
キリシタン資料篇では、ポルトガル語の文法書と辞書を用いて、オ段長音の開合、日葡辞書の和訳の問題と「請け負ふ」「アサガレイ(朝餉)」「サメ・フカ・ワニ」の語義について論じる。
凡例
語法篇
第一章 推定伝聞の助動詞「なり」について―その承接と意味―
第二章 今昔物語集の「今夜」と「夜前」と
第三章 源氏物語の「給ふる」「侍り」について
第四章 「申す」「聞えさす」「聞ゆ」―官位・身分・人名を承ける場合について―
第五章 中世の敬語―受益敬語について―
第六章 「御導師遅く参りければ」の解釈をめぐって
語彙篇
第七章 源氏物語用語の清濁について
? 首書源氏物語の「ときとき」と「ときどき」
? 「調す」清音のこと
? 「螺鈿」は「ラテン」であった
第八章 「けそん」は「家損」なりや―源氏物語用語考―
第九章 「ウソ」の語源
第十章 「ハッケヨイ」の語源
キリシタン資料篇
第十一章 オ段長音の開合について―ロドリゲス『日本文典』覚書―
第十二章 日葡辞書の和訳について
第十三章 日葡辞書のVqev?の語義―ficar deuendoの訳語について
―
第十四章 「アサガレイ(朝餉)」のことなど―日葡辞書のことば―
第十五章 日葡辞書の「サメ」「フカ」「ワニ」について
岡崎正継[オカザキ マサツグ]
昭和九年高知県に生まれる。
國學院大學助手、助教授、教授を経て、現在、國學院大學名誉教授。
博士(文学)。
著書
『国語助詞論攷』(平成8年、おうふう)
『古典文法 別記』(平成3年、秀英出版、共著)
内容説明
五十年に亙る研究成果を語法篇・語彙篇・キリシタン資料篇の三篇に収める。語法篇では、推定伝聞の助動詞「なり」、助動詞「つ」「き」の用法、「申す」「聞こえさす」「聞こゆ」の敬意の差、受益敬語「てたぶ」の成立などについて論じ、語彙篇では『首書源氏物語』に見られる清濁や「ウソ」「ハッケヨイ」の語源について考察する。キリシタン資料篇では、ポルトガル語の文法書と辞書を用いて、オ段長音の開合、日葡辞書の和訳の問題などについて取り上げる。
目次
語法篇(推定伝聞の助動詞「なり」について―その承接と意味;今昔物語集の「今夜」と「前夜」と;源氏物語の「給ふる」「侍り」について;「申す」「聞えさす」「聞ゆ」―官位・身分・人名を承ける場合について;中世の敬語―受益敬語について;「御導師遅く参りければ」の解釈をめぐって)
語彙篇(源氏物語用語の清濁について;「けそん」は「家損」なりや―源氏物語用語考;「ウソ」の語源;「ハッケヨイ」の語源)
キリシタン資料篇(オ段長音の開号について―ロドリゲス『日本文典』覚書;日葡辞書の和訳について;日葡辞書のVqev^oの語義―ficar deuendoの訳語について;「アサガレイ(朝餉)」のことなど―日葡辞書のことば
日葡辞書の「サメ」「フカ」「ワニ」について)
著者等紹介
岡崎正継[オカザキマサツグ]
昭和9年高知県に生まれる。國學院大學助手、助教授、教授を経て、國學院大學名誉教授。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
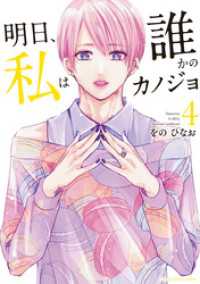
- 電子書籍
- 明日、私は誰かのカノジョ(4) サイコ…