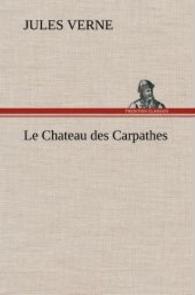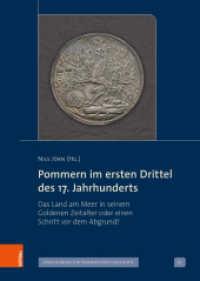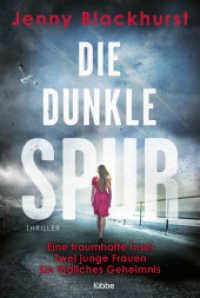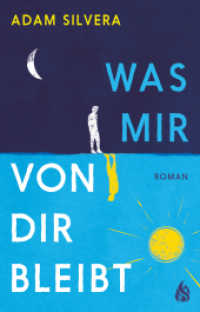内容説明
翻案小説の名手・太宰治。その魅力は尽きることなく根を張りめぐらせて時代を超えていく―。太宰の作品を地下深く掘り下げていくと、したたかで豊かな地下茎に出遭う。日本の古典や海外の名作がそれだ。本書は知られざる「太宰と外国文学」を切り口に、作品の生成に秘められた世界を開示・検証し、研究成果としては初めての一書として世に問うものである。
目次
太宰治のシラー受容―「走れメロス」の素材について
太宰治とシラー―太宰の作品におけるシラーの影響について
太宰治とオイレンベルク―「女の決闘」の背景
「女の決闘」論―太宰の外国文学受容の視点から
太宰治とクライスト
「乞食学生」と外国文学
太宰治のカフカ受容―「花火」を中心として
「人魚の海」の比較文学的考察
『お伽草紙』と異郷淹留説話―「浦島さん」成立の背景について
『お伽草紙』とグリム童話
変身と再生―「魚服記」試論
太宰治と「お化け」のホフマン―太宰のドイツ文学受容について
飛鳥定城と太宰治―作家「太宰治」誕生の頃
著者等紹介
九頭見和夫[クズミカズオ]
1942(昭和17)年福島県生まれ。東北大学大学院文学研究科(独語・独文学専攻)修了。福島大学教育学部教授。東北大学、山形大学、高知大学等で非常勤講師。日本独文学会(1997年度から2年間理事)、日本比較文学会、日本近代文学会等会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。