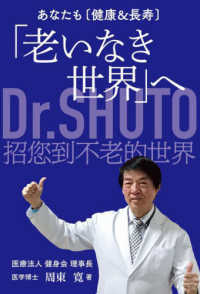出版社内容情報
現実経済に無知な経済学者とデタラメな理論に振り回されないために経済の正しい知識を身につけよう
リフレ政策、財政均衡主義、消費税増税、TPP、グローバリズム、規制緩和、成長戦略...日本経済と国民生活を痛めつける間違いだらけの経済政策に今こそNO!
人気メルマガ「三橋貴明の「新」日本経済新聞」の寄稿者が間違いだらけの経済政策を斬る!
はじめに ――“温かい心”を失った経済学
序章 経済学者を信じてはいけない
財政破綻で国民を脅す現代の狼少年
経済の目的は「世を経め、民を済う」こと
マルサスとリカードの“陰鬱な”経済理論
政治家は過去の経済思想の奴隷
アベノミクスの変節からわかる安倍首相の本音
第1章 現代経済学の誕生と成長
経済学者が嘘をつく理由
経済学説史上のエポック・メイキング「限界革命」
パレート最適が完成させた新古典派経済学
現実の分析を目指したケインズとシュンペーター
ケインズ経済学がもたらした衝撃
新古典派への揺り戻し
ポパー主義が経済学者に与えた影響
リーマン・ショックに呆然とした主流派経済学
第2章 規制反対のネオリベ経済学と利益誘導型の俗情経済学
経済理論と経済政策の間には深く大きな溝がある
主流派経済学者にとって「不況」は存在しない!?
誰の顔も同じに見える主流派経済学のメガネ
使命を忘れたペンギン
プラグマティズムに背を向けた経済学者
最新理論「動的一般均衡」は役に立たない
理論とイデオロギーの結合したネオリベ経済学
市場原理主義と新自由主義
レーガノミクスと滴り落ちる毒
トリクルダウン政策を支持するエリートたち
主流派経済学も一枚岩ではなくなった
俗情経済学がもたらす脅威
第3章 主流派経済学には非自発的失業者は存在しない
不都合な現実を消し去る手品
主流派経済学の景況感
ベッドの長さに合わせて足を切る
不都合な現実と経済学の制度化
数学が共通言語になった
非自発的失業をどうやって消し去るか
各個人を金太郎アメの断面とみなす理論
宙に浮く循環的失業
ミスマッチ失業は自己責任か
第4章 統計数値は信用できるか
失業者という“厄介な”存在
理論と現実をつなぐ統計数値
改ざんされた潜在GDPの定義
平均は現実に近づき、現実を理想と化す
潜在成長率をめぐる大いなる誤解
潜在成長率のパラドックス
今や「完全失業率」も信用できない!!
主流派経済学による完全雇用の新定義
第5章 錯綜する理論と現実
「新種の経済学者」の誕生
教科書経済学者のトライアングル
理論と現実を足して二で割る
中央銀行の経済学離れ
日本銀行の先祖がえり
理論と現実の接点としての統計
第6章 現実を分析する経済社会学
経済理論を現実の場へ引き出す
複雑な社会をどう理解するか
経済学はほかの学問と連結できるのか
主流派経済学は人間を社会的存在とみなさない
道徳心こそが利己心をコントロールできる
現実に即した新しいミクロ理論が必要になる
シュンペーターとケインズに学ぶ
「理論付けられた現代」を語るには
第7章 経済効率の正しい考え方
あなたは「効率」に抵抗できるか?
方法の選択が効率性を決める
グローバル化が効率性の意味を変えた
効率性と資本の運動法則
「無国籍」な資本の増殖が加速する
効率の「二律背反」とどのように向き合うか
効率至上主義が間違っている理由
第8章 経済社会学による財政再建論
政府は一体いくらまで借金できるのか?
財政問題に関する一般論
財務省脳が日本経済を破壊する
景気が決める国債発行の是非
政府の借金の返済方法は三つ
財政ファイナンスを危険視する愚かな人々
借金を不況に肩代わりさせる
無税国家と出口戦略
第9章 リフレ派の理論ではデフレを脱却できない
矛盾だらけの「パッチワーク経済学」
リフレ派とネオリベ派の出合い
リフレ派の二階建て理論
リフレ政策の成立要件「期待形成の国民的一致」は可能か
マクロ的諸要因の決定は貨幣現象なのか?
「インフレ期待」は人々の錯覚を期待
実質賃金は永遠に上がらない
実物投資と金融投資の混同
量的緩和の限界と弊害
第10章 アベノミクスの過去・現在・未来
主流派政策の逆を行なったアベノミクスだったが……
初期アベノミクスの二つの意義
事実誤認によるアベノミクスの転換
意地の果てのバブル
成長戦略は公共を破壊する
今こそ、大胆な政策転換を!
国債は「日銀が買って、政府が売る」
【著者紹介】
1956年、神奈川県生まれ。1980年、早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。1986年、同大学大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退学。1996年、帝京大学助教授。2007年、帝京大学短期大学教授(2014年退職)。現在、東海大学非常勤講師および会社役員。専門は、経済変動論、シュンペーター研究、現代日本経済論。主な著書に『経済学とはなんだろうか -現実との対話-』(八千代出版、2012年)、『シュンペーター理論の展開構造』(御茶の水書房、1987年)。
内容説明
現実経済に無知な経済学者とデタラメな理論に振り回されないために、経済の正しい知識を身につけよう。リフレ政策、財政均衡主義、消費税増税、TPP、グローバリズム、規制緩和、成長戦略…人気メルマガ「三橋貴明の「新」日本経済新聞」の寄稿者が間違いだらけの経済政策を斬る!
目次
序章 経済学者を信じてはいけない
第1章 現代経済学の誕生と成長
第2章 規制反対のネオリベ経済学と利益誘導型の俗情経済学
第3章 主流派経済学には非自発的失業者は存在しない
第4章 統計数値は信用できるか
第5章 錯綜する理論と現実
第6章 現実を分析する経済社会学
第7章 経済効率の正しい考え方
第8章 経済社会学による財政再建論
第9章 リフレ派の理論ではデフレを脱却できない
第10章 アベノミクスの過去・現在・未来
著者等紹介
青木泰樹[アオキヤスキ]
1956年、神奈川県生まれ。1980年、早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。1986年、同大学大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退学。1996年、帝京大学助教授。2007年、帝京大学短期大学教授(2014年退職)。現在、東海大学非常勤講師および会社役員。専門は、経済変動論、シュンペーター研究、現代日本経済論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さきん
ケイ
NORI
ブック
ドクターK(仮)
-
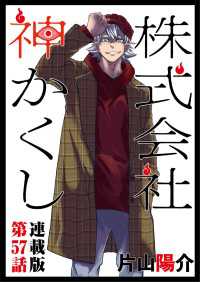
- 電子書籍
- 株式会社 神かくし 連載版 第57話 …
-

- 電子書籍
- 今日からあなたの護衛です ~王太子殿下…
-
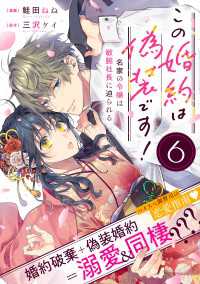
- 電子書籍
- この婚約は偽装です! 名家の令嬢は敏腕…
-

- 電子書籍
- RIDERS CLUB No.461 …