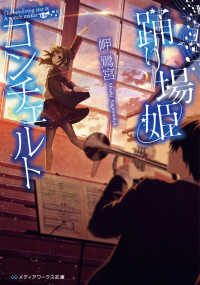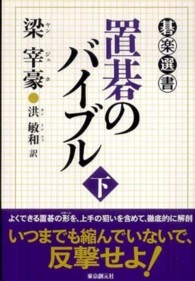内容説明
不妊治療、出生前診断、人口政策など、出産に関わる文化、経済、政治について医療人類学の見地から深く考察する。
目次
第1章 「ミクロ」に「ローカル」を見る―数の論理と女性の生
第2章 産みの風景をたどる
第3章 「あらかじめ知る」ことのためらいと不安―出生前検査
第4章 尋ねないことと説明しないこと―超音波検査
第5章 「自分たちの子」をもつために―代理出産と親子関係
第6章 「普通の家族」と「本当の」親―提供精子と提供卵子
第7章 なぜ不妊治療を求めるのか
著者等紹介
柘植あづみ[ツゲアズミ]
1960年三重県生まれ。明治学院大学社会学部社会学科教授。専攻は医療人類学。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程退学。博士(学術)。北海道医療大学を経て現職。おもな著作に、『文化としての生殖技術』(松籟社、1999年。第20回山川菊栄賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
かなで
3
「どうして出生前診断をしなかったことをなぜとは聞くのに、出生前診断をした人になぜ、と聞かないのか」という話が自分にもあった経験だったので面白かった。多数派になぜ、と聞いてもそれが当たり前で考えたことがない、という人が多いのではないか、と。当たり前のことこそ考えてみなければならないだろうなーと思った。(ちなみに私の経験は友達に「どうして死にたいと思うのか?」と聞かれたので「どうして生きていたいと思うの?」と聞いた経験。その友達はその考えがなかったからその質問にびっくりした、と言ってた)/36冊目2020/11/18
飯田一史
2
超音波検査の安全性については、短期的には胎児の影響はほとんどなく安全とされているが、危険だという結果が出ていないだけでどんだけ浴びても影響がないとはわかっておらず、超音波が胎児のストレスになっている可能性もあるからカナダなどでは検査回数を必要最小限に抑えた方がよいとされているのに日本では2週にいっぺんくらいやっている&そのせいで自分の腹に胎動が起こる以前にエコー写真を見て妊娠を実感するのが近年の日本人女性の胎児観の特徴だと書いてあり目からウロコ。2015/05/26
くろなんとか
2
日本における不妊治療の根底にある意識とは何か、生殖医療に関する医者および受ける側の詳しいインタビューが書かれていて考えさせられる。そこから出された、不妊は社会的な病気でありスティグマだという言葉が印象的だった。また、諸外国の女性の妊娠に対する意識調査や、日本におけるお産の歴史、途上国の人工抑制政策と先進国の思惑など、生殖に関する様々な状況を知ることができて良かった。生殖におけるジェンダーバイアスについても考えさせられる。2014/04/09
takao
1
ふむ2020/02/15
あいち
1
読んでみて、知らなかったことはたくさんあるのだと思った。提供精子の人工授精が普通に行われていることに驚いたし、検査におけるリスクもあるのだと知った。不妊治療は自然なことではないと思っていたけれど、人間にできることには限界があり、その範囲の中でしている限りはそれも自然なのだという言葉には、なるほどなあと、共感も覚える。倫理の問題、社会学・・・内包している問題は複雑だけれど、これを読んでその一端を見れてよかった。2012/12/08