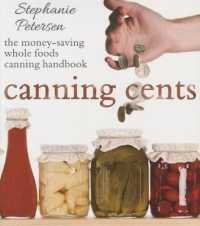出版社内容情報
新進研究者による、ナショナリズム論の新たなる地平を拓く力作。
内容説明
混迷するグローバリズムのもと、さすらうことが常態化した現代に、「国家」や「ナショナリズム」が示す新しい意味とは何か。アレントの「故郷喪失者」をキーワードに“パーリア”としての現代人の姿を浮き彫りにし、ナショナリズムの可能性をおしひらく21世紀の新たな「国家論」。
目次
序 「近代」の極北にて―自覚なきパーリアたちの群れ
第1章 ナショナリズムの最期?
第2章 「市民」のナショナリズム
第3章 パーリアたちの帰郷
第4章 ナショナリズムの復興―「故郷」回復への道行き
結 ネイションとの再会
著者等紹介
黒宮一太[クロミヤカズモト]
1972年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。現在、京都文教大学勤務。専攻は政治思想、政治哲学。理論研究、思想的考察を中心に、ナショナリズムおよび国家についての考察を行う。ほかに『発言者』、『表現者』の各誌で社会評論、書評を発表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
politics
3
シヴィック、リベラル・ナショナリズムやエスノスンボル論などのナショナリズム論を渉猟しつつ、そこにアレントの「故郷喪失」の議論を持ち込み、ナショナリズム論に接続させようとする意欲作。アレントの議論がそこまでナショナリズム論および日本ネーションに上手く適応出来ているのかは疑問ではあるものの、大変興味深い内容であることは間違いない。著者の議論に坂本多加雄氏の「国民の物語」論を繋ぎ合わせることができれば良いではと思ったが、著者のその後のナショナリズム論があればと感じた。2022/06/22
直井
1
日本国民としての一体性を否定しようとは思わないけれど、国家の標榜する「愛国心の涵養」には右傾化を感じずにはいられない。何故そう感じてしまうのか、という点において参考になった。 私たちは確かに文化的・民族的に「根無し草」となっている。しかしそれならば、先祖が残した「遺産」を受け取ることも出来ないと思う。寧ろ受け取れないことが自明になっている世界の中に生きていることを認め、具体的な文化の中から目に見えない思考様式を探し出す、という思考を行うべきなのではないか、と私は思います。2013/12/06
manmachine
0
良書。アンダーソンやゲルナーといったナショナリズム論の古典から、コーン、イグナティエフ、ルナンといった「シヴィック・ナショナリズム」およびタミールの「リベラル・ナショナリズム」を批判的に検討しつつ、アンソニー・スミスによるエスニシティへの共鳴を経て、アレントの読解へと至る。ナショナリズム論の教科書としてもよく纏まっていると同時に、著者の「保守主義者」としての立場も鮮明に打ち出されている。ただ、後半は多少繰り返しが多い。でも、読んでよかった。2009/10/07