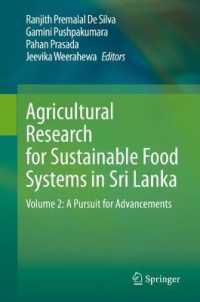出版社内容情報
私たちの日常は、あまりにも生き物だらけだ!
本書は、身近にいる生き物を、小さなものはウイルスから虫や鳥、大きなものはクマやマグロまで、そしてもちろん私たちヒトもふくめて、ぜんぶで63とりあげました。
生活の中にいつも登場する生き物の"おもしろい話"がいっぱいです!
そういえば疑問に思うこと、いわれてみれば気になること、そんな生き物のナゾにせまります。
・ゴキブリは3億年前から変わらない「生きた化石」?
・ミミズはなぜ夏の炎天下で干からびているの?
・地球史上最大の昆虫はトンボだった?
・伝書鳩はなぜ手紙を届けられるの?
・なぜウグイス色は黄緑色と思われている?
・多量の汗をかくのはウマと人間だけ?
・高級和牛はほぼ1種からつくられている?
・カルガモはなぜ春になると引っ越しするの?
・カエルは胃袋をはき出して洗うって本当?
思わずだれかに話したくなる!
教科書や図鑑のような解説ではなく、「どう身近なのか」「私たち人間との関係性」を軸にして、「へ‾そうなんだ」と思える話がたくさん登場します。
暮らしに役立つ生き物の知識が、毎日の生活に彩りを与えてくれる、そんな1冊です!
◎目次
第1章?『家の中・庭』にあふれる生き物
第2章?『公園・学校・市街地』にあふれる生き物
第3章?『野山・田畑・牧場』にあふれる生き物
第4章?『水辺・川・海』にあふれる生き物
第5章? 私たち『ホモ・サピエンス』
◎著者より
本書は、次のような人たちに向けて書きました。
・めずらしい生き物もいいけど、もっと身のまわりにたくさんいる「身近な生き物」について知りたい!
・教科書や図鑑のような解説ではなく、「私たちの生活とその生き物がどう関係しているのか」がわかるようなおもしろ知識を知りたい!
昨今、学校で教える「理科・生物」が、具体的な生物(まさに生き物! )から遠ざかり、抽象的になっている感じがします。
私たちは、日常で出会う生き物たちに好奇心がわくような「理科・生物」の学びであってほしいと願っています。
本書を執筆するときにとくに意識したのは、「虫が嫌い! 見るのも触るのもイヤ! 」などという人です。
というのは本書執筆前に、小学生女子向けの理科の本の監修を頼まれて打ち合わせをしたのですが、「テーマに虫嫌いが多いので内容に虫のことは入れないんですよ。入れてもせいぜいチョウやトンボくらい」といわれたからです。
私は、そんな人にこそ、自然のふしぎ、自然のおもしろさを感じてもらい、触らなくてもいいから、嫌いな生き物であっても、その生活に興味をもってもらいたいと思うのです。
左巻 健男[サマキ タケオ]
著・文・その他
内容説明
日常は、あまりにも生き物だらけだ!生き物のナゾを解き明かそう。
目次
第1章 『家の中・庭』にあふれる生き物(ウイルス―「汗をかいたらカゼが治る」はまちがい?;細菌―抗生物質は使われすぎると危険? ほか)
第2章 『公園・学校・市街地』にあふれる生き物(ダンドムシ(団子虫)―迷路の中を迷わずゴールできる?
ハチ(蜂)―怖いのは毒ではなくアレルギー反応? ほか)
第3章 『野山・田畑・牧場』にあふれる生き物(バッタ キリギリス コオロギ スズムシ(鈴虫)―鳴く虫の“耳”はどこにある?
カマキリ―なぜメスは交尾中にオスを食べてしまう? ほか)
第4章 『水辺・川・海』にあふれる生き物(アメンボ―水に洗剤を入れると沈んでしまう?;カエル(蛙)―胃袋をはき出して自分で洗うって本当? ほか)
第5章 私たち『ホモ・サピエンス』(どんどん増えるホモ・サピエンス;ヒトの進化と直立二足歩行 ほか)
著者等紹介
左巻健男[サマキタケオ]
法政大学教職課程センター教授。専門は、理科・科学教育、環境教育。1949年栃木県小山市生まれ。千葉大学教育学部卒業(物理化学教室)、東京学芸大学大学院教育学研究科修了(物理化学講座)、東京大学教育学部附属高等学校(現:東京大学教育学部附属中等教育学校)教諭、京都工芸繊維大学教授、同志社女子大学教授等を経て現職。『理科の探検(RikaTan)』誌編集長。中学校理科教科書編集委員・執筆者(東京書籍)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ユウユウ
アキ
G-dark
スプリント
みちぱん