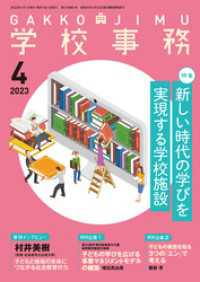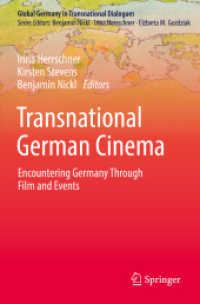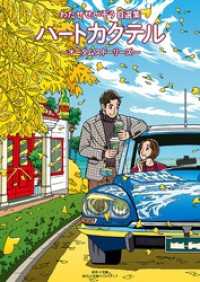出版社内容情報
ロマン主義から現代美術へと至る美術表現を綺想という芸術的感性で解読し、芸術創造の霊感源「存在の充足」を探る。
内容説明
連鎖する芸術の眩惑的融合、不可視へ侵入する想像力。五感を震憾させる美への慧眼が召喚する綺想というイメジャリーのクリティシズムが遊走するプラーツ美学の精髄。
目次
1 美術批評の言語
2 空間恐怖
3 神の操り人形
4 広大にして未知なる領域
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
傘緑
39
「どんな殴り描き、ぼろくずの寄せ集め、絵具のマチュドニアでも芸術だと主張…『犬は犬づれ、とく失せよ!』」「おそらく将来の歴史家は、抽象芸術はX年に起きるはずの火星人の大襲来を考慮して、その奇怪、異様、非人間的な様相にあらかじめ慣れておくに用意周到に準備されたものであったと言うのではないだろうか」「アヴァンギャルド以降の二十世紀美術は、十九世紀の美術がかろうじて保持していた『人間性』をすでに喪失して反人間的なフォルムを尊重する非芸術と化した…もはや芸術と呼ぶに値しない…それがプラーツの主張(訳者あとがき)」2017/04/05
roughfractus02
5
ロマン派に蛇(悪魔)-林檎(知)-イヴ(官能美)-アダム(想像力)の関係の原初イメージを見出す著者は、ロマン派以後の芸術に保守的態度で臨む。歴史の中に原初の物語の反復を見出す著者は、本書で自ら歴史と物語に留まるかに見える。人間や英雄を主人公とし、線状の時間に沿って因果関係的に進む物語世界は、紙製メディアと共に主体的人間なる単位を作り出した。著者はロマン派に主体的人間の中の無秩序への傾向を見る一方、次世代美術に非芸術/非人間/反物語を見る。著者には機械的抽象的な後者は不気味の谷の向こうの異質な何かのようだ。2019/09/10
Yosuke Saito
0
イタリアの美術史家プラーツの諸論考をまとめたアンソロジー。その対象はマニエリスム、新古典主義、ロマン主義、そして現代美術と幅広い。とりわけ、もはや「新しい美術史」とも呼べなくなってきたニュー・アート・ヒストリーへの批判も含め刺激的な論考がよい。個人的には、「芸術と無秩序」、「ダヴィッドからドラクロワへ」、「英雄的な「ポンピエ」たち」、「リキュールのオルガン」が面い。2011/11/27