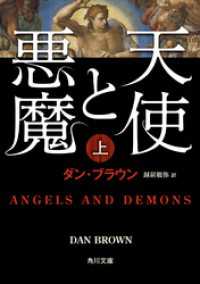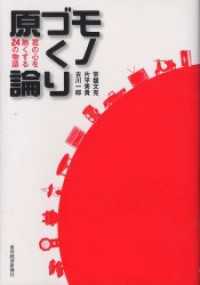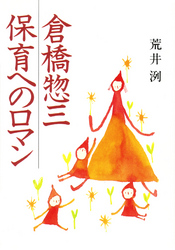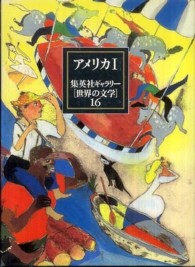- ホーム
- > 和書
- > 社会
- > 社会問題
- > マスコミ・メディア問題
内容説明
ピューリッツア賞受賞特派員が追った次世代メディアの覇権をめぐる十年史。
目次
1 陰謀(HDTV…それだ!;ワシントン、救助に乗り出す)
2 プレーヤーたち(やつらは俺たちを追い出した;身代を食いつぶす ほか)
3 テスト(ゴールデンアイとフーヴァー・テスト;それを作るのはあなた ほか)
4 政治(グランドホテルの週末;真鍮のネズミ ほか)
著者等紹介
ブリンクリー,ジョエル[Brinkley,Joel]
ワシントンDC生まれ。75年に首都のノースカロライナ大学を卒業。70年代から80年代にかけてAP通信の記者として、バージニア州リッチモンドの『ニューズ・リーダー』およびケンタッキー州『ローズヴィル新報』などで働く。79年、東南アジアに派遣され、ベトナムのカンボジア侵攻、ポル・ポトによる大虐殺とその成り行きについて取材し、これらの報道により80年にピューリッツア賞を受賞する。83年10月ワシントン勤務を機に同社を退社、『タイムズ』記者となり、アメリカのレバノン干渉、国際麻薬組織、ニカラグア反戦などを取材。またイラン革命の報道責任や、レーガン政権最後の年はホワイトハウス担当記者を務める。88年3月にエルサレム支局長としてイスレエルへ赴き、パレスチナ暴動を発端とする湾岸戦争へと取り組む。91年にワシントン支局に戻り、長期的な調査・研究プロジェクトの総括責任記者となる。98年にニューヨーク支局へ異動し、記者および編集委員として、政治面およびTWA800便墜落事故の報道記事などの責任編集を担当。97年から98年にかけて、デジタルテレビへの移行について精力的に取材、記事を発表する。98年にワシントンに戻り、政治コラムニストとなる。過去15年間のうちに、1ダースを超える国際的なジャーナリズムや記者の賞を受賞している。『ニューヨーク・タイムズ』の記者、編集委員、およびピューリッツア賞受賞特派員として活躍している
浜野保樹[ハマノヤスキ]
東京大学大学院新領域創成科学研究科助教授。1951年生まれ。国際基督教大学教養学部卒業。80年国際基督教大学大学院博士後期課程単位取得退学。87年ハーバード大学・教育大学院教育工学センター客員研究員、バンドストリート教育大学・子供とテクノロジー研究所客員研究員、メディア教育開発センターを経て、現職。メディア論専攻。マルチメディアの研究開発に従事する。黒沢明文化振興財団理事。主な著書に『極端に短いインターネットの歴史』(97年/昌文社)、『メディアの世紀』(91年/岩波書店)、『デジタル革命の衝撃』(96年/ペンローグ)他多数。訳書に『アラン・ケイ』(92年/アスキー)、『情報スーパーハイウェイ』(94年/電通)など
服部桂[ハットリカツラ]
朝日新聞社企画報道室。1951年生まれ。78年早稲田大学理工学部電子工学課程修了、朝日新聞社に入社。87から89年MITメディアラボ研究員、89年、科学部記者としてコンピュータや情報通信を担当。91~93年『ASAHIパソコン』副編集長。95年、デジタル出版部編集委員として『DOORS』を手がける。98年より『Paso』編集長。2001年3月より現職。主な著者に『人工現実感の世界』(91年/工業調査会)、『人工生命の世界』(94年/オーム社)、『メディアの予言者』(2001年/広済堂出版)、『移動する生地』(共著、99年/NTT出版)など。訳書に『ハッカーは笑う』(95年/NTT出版)、『人工生命』(96年/朝日新聞社)、『デジタル・マクルーハン』(2000年/NTT出版)、『「複雑系」を超えて』(監修、99年/アスキー)がある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。