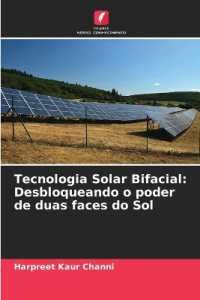出版社内容情報
平成18年に信託法が全面改正されたことにより、家族信託の利用者が増える一方、士業など支援者の責任が問われる裁判が増えている。現在は、契約書の作成の責任追及が主体となっているが、今後はそれに加えて「税金」について支援者の説明義務が問われる訴えも起きてくるものと思われる。本書では、信託税制と難題と言われている「遺留分問題」「債務控除問題」及び「相続税法9条の4と同9条の5の矛盾」について解説。
【目次】
第1章 家族信託の制度について
はじめに
1 家族信託制度とは
2 信託行為とは
3 信託財産になる財産とは
4 信託の種類
5 信託の機能について
(1)「財産の分別管理機能」について
(2)「倒産隔離機能」について
(3)「財産の転換機能(物権の債権化機能)」について
6 受託者の義務
7 受益者の権利等
8 相続対策としてのメリット
(1)認知症等になった親の財産管理が容易に行える。
(2)遺言書の代わりとして使うことができる。
(3)相続における財産承継の順番付けが行える。(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)
9 不動産を信託した時の登記簿の表示
10 預貯金口座を信託した時の口座名の表示
11 信託の開始
12 信託の変更
(1)関係当事者の合意等に基づく場合
イ 委託者、受益者及び受益者の合意がある場合(信託法149①)
ロ 信託の目的に反しないことが明らかであるとき(信託法149②)
ハ 受託者の利益を害しないこと等が明らかであるとき(信託法149③)
ニ 信託行為に別段の定めがある場合(信託法149④)
ホ 委託者が現に存在しない場合(信託法149⑤)
13 信託の終了
14 信託の清算
15 残余財産の帰属
16 その他の登場人物
【信託監督人】
【信託管理人】
【受益者代理人】
第2章 家族信託の税金について
【所得税制の考え】
1 はじめに
2 税制上の信託の分類
3 信託の課税のタイミング及び課税対象者
4 受益者等課税信託の課税について
(1)所得税法第13条第1項の「みなし規定」について
イ 「受益者としての権利を現に有するものに限る。」について
(2)所得税法第13条第2項の「みなし受益者」について
イ 「信託の変更をする権限を現に有している」について
ロ 「信託財産の給付を受けることとされている者」について
(イ)「停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者」について
(3)「信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属」について
イ 「信託が一部の受益者にしか特定されていない場合の受益権の所在」
(イ)ある特定の受益者の有する権利が、全体の一部であり、他の受益者が存しない場合
(ロ)受益者としての権利を有する受益者が複数人いる場合
(ハ)収益受益権と元本受益権との分割
a 元本と収益との受益者が同一人物の場合
b 受益者が複数の場合
c 元本と収益との受益者が異なる場合
(4)「遺言代用信託における受益者の税務上の扱い」について
5
内容説明
平成18年に信託法が全面改正されたことにより、家族信託の利用者が増える一方、士業など支援者の責任が問われる裁判が増えています。現在は、契約書の作成の責任追及が主体となっていますが、今後はそれに加えて「税金」について支援者の説明義務が問われる訴えも起きてくるものと思われます。本書では、信託税制と難題と言われている「遺留分問題」「債務控除問題」及び「相続税法9条の4と同9条の5の矛盾」について解説しました。
目次
第1章 家族信託の制度について(家族信託制度とは;信託行為とは;信託財産になる財産とは ほか)
第2章 家族信託の税金について(【所得税制の考え】;【所得税(法人税)関係】
【贈与税(相続税)関係】 ほか)
第3章 その他(信託と民法上の遺留分の関係;信託と相続税法上の債務控除の関係;相続税法第9条の4と同9条の5の矛盾)
著者等紹介
山田吉隆[ヤマダヨシタカ]
大分県出身。昭和45年4月熊本国税局採用。平成31年3月公益社団法人天王寺納税協会専務理事(退任)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 僕らのポリリズム 1 プリンセス・コミ…