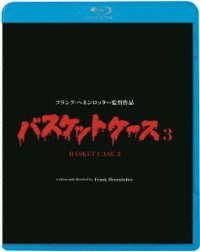出版社内容情報
租税は、納税者から徴収するのが原則だが、それができない場合の措置として、第三者から徴収する各種の制度が用意されている。その中で、最も活用度が高く重要視されている第二次納税義務制度は、納税者の財産が合法的にその支配から逸脱した場合において、特別な第三者に補充的に納税義務を課すことにより、租税徴収の確保を図ろうとするもの。このような第二次納税義務の重要性にかんがみると、徴収職員としては、当該制度に精通することが不可欠なことはいうまでもなく、納税者としては、予防法学的な観点から、また税理士等職業専門家としては、納税者の相談に万全を期すためにも、第二次納税義務制度に通暁することが求められる。
本書は、第二次納税義務制度が一般的にはなじみの少ない制度であることから、誰もが容易に理解できる内容になるよう配慮した。第二次納税義務に類似する制度との関係を明らかにし、第二次納税義務の追及の可否に関する判断に資するとの観点から、多くの裁決事例や裁判例について、コメント・解説を付して紹介している。
【目次】
第1編 国税徴収法の理念 ―第二次納税義務の位置づけー
第1章 租税徴収制度調査会答申から
1 租税徴収の確保
2 私法秩序の尊重
3 徴収制度の合理化
4 徴収法の内容
第2章 国税徴収法の特色
1 租税債権の確保
2 私法秩序の尊重
3 納税者の保護
4 地方税・公課の徴収に関する法令
(参考)地方税の滞納処分の根拠条文
第3章 租税徴収手続の概要
1 滞納処分
2 租税徴収手続の流れ
(参考)租税徴収手続の流れ図
第2編 第二次納税義務制度
第1章 趣旨
1 第二次納税義務の拡充
2 低額譲渡の場合の第二次納税義務の問題
3 地方税の第二次納税義務
(参考)第二次納税義務制度一覧表
第2章 第二次納税義務追及の着眼点
1 概説
2 各種の第二次納税義務追及の着眼点
3 滞納整理の進行過程からみた第二次納税義務追及の着眼点
4 滞納者をとりまく諸現象からみた第二次納税義務追及の着眼点
第3章 手続
1 納付の通知
2 納付催告書による督促
3 第二次納税義務者の財産の換価制限
第3編 第二次納税義務制度に類似する制度
第1章 譲渡担保権者の物的納税責任
第1節 概説
1 法令
2 趣旨
第2節 手続
1 譲渡担保権者に対する告知等
2 譲渡担保財産に対する滞納処分
3 差押先着手優先等の特例
4 設定者の財産として差し押さえた場合
5 譲渡担保財産が確定的に譲渡担保権者に帰属した場合
第3節 譲渡担保財産からの徴収
1 譲渡担保財産
2 徴収不足の判定
3 手形の譲渡担保の除外
4 譲渡担保財産が集合物又は有価証券の場合
5 譲渡担保財産が将来発生すべき債権である場合
第4節 譲渡担保財産の証明
1 譲渡に係る権利の移転の登記がない場合
2 集合物の譲渡担保に対する取扱い
第5節 債権譲渡登記を利用した集合債権譲渡担保
1 債権譲渡登記制度
2 債権譲渡登記の調査
3 「担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合」の解釈
第6節 譲渡担保債権と租税債権との競合
1 集合債権譲渡担保の第三者対抗要件
2 一括支払システム
第7節 譲渡担保権者の物的納税責任に係る裁判例
第2章 保証人の納税義務
第1節 概説
1 納税保証人
2 保証契約の締結
第2節 要件
1 保証人に対する滞納処分開始の要件
2 保証人の履行と主たる納税者の租税
3 第二次納税義
目次
第1編 国税徴収法の理念―第二次納税義務の位置づけ―
第2編 第二次納税義務制度
第3編 第二次納税義務制度に類似する制度
第4編 第二次納税義務の通則
第5編 第二次納税義務の追及
第6編 第二次納税義務をめぐる諸問題
著者等紹介
橘素子[タチバナモトコ]
昭和57年3月明治大学法学部法律学科卒業。同年4月東京国税局に採用。東京国税局、東京国税不服審判所、麹町税務署等において勤務。令和2年4月日本大学経済学部大学院経済学研究科租税研究コース講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
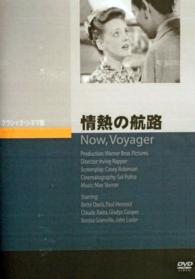
- DVD
- 情熱の航路