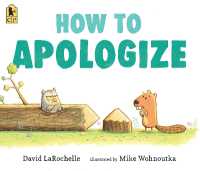出版社内容情報
相続財産の評価については、法令、通達の他、国税庁から通達改正に伴う情報や質疑応答等も公表されており、以前に比較すれば、情報量としてはかなり多くなっていると思います。
ただ、それらの情報を整理し、また、それ以外の裁決や判決内容をも確認していくとなると、相当な作業となります。一方で、詳細な情報を得ることで、財産の評価額が大きく変わることもあり得ます。また、申告した内容の中でも財産評価の責任は、基本的に税理士が持つようになるかと思います。よく税務調査で、名義借預金の存在が問題となり、修正申告の対象となったりしますが、これとはかなり相違する部分があります。最近では、相続税評価か時価評価か、いわゆる総則 6 項の問題も話題になっています。
本書は、法令、通達、国税庁からの各種情報、裁決、判決等を実務にどれだけ活かせるのかを目的として執筆しました。そのため、できるだけ根拠を明確にし、判断の目安的なものを目指しました。
内容説明
判断が難しい評価について実務家目線の考え方・方向性を解説。法令・通達・判決、参考情報を多数収録し、実務への応用が可能。随所に図表を使用し、項目ごとにポイントを設けて論点整理。
目次
土地編(時価評価;評価単位;画地調整・特定路線価;貸家建付地;借地権・耕作権;その他)
建物編(家屋が建築中や建築直後で固定資産税評価額が付されていない場合;相続開始前に増改築等が行われている場合、リフォームが行われている場合)
株式編(法人が不動産購入後、3年経過後に相続が開始した場合の株価評価と留意点;課税時期前3年以内に不動産を購入し、課税時期までに価額が下落した場合 ほか)
著者等紹介
渡邉正則[ワタナベマサノリ]
昭和58年学習院大学経済学部卒業。東京国税局税務相談室、同課税第一部調査部門(地価税担当)等の主に資産課税に係る審理事務に従事。平成9年8月税理士登録、中小企業診断士、CFP、青山学院大学大学院(会計研究科)客員教授
関口一男[セキグチカズオ]
中央大学法学部政治学科卒業。税務署(荒川、杉並、葛飾、武蔵野、玉川)、東京国税局、東京国税不服審判所において、主として資産課税(相続税、贈与税、財産評価、譲渡所得、地価税など)事務に従事後、現在、税理士、不動産鑑定士補(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。