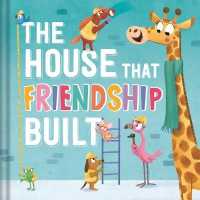出版社内容情報
平成元年4月に創設された消費税は、今年で30年目に入っています。
平成31年10月からは、標準税率の10%への再引上げと併せて、「飲食料品(酒類及び外食を除く)」と「新聞」を対象として税率を8%に据え置く軽減税率制度が導入される予定です。
本書は、税務関係民間団体である間税会として、円滑な税務運営に協力する観点から、軽減税率制度について事業者の方々が誤りなく適正に適用されることを願い、出来るだけわかりやすく解説しました。
発刊にあたって
はしがき
第一 消費税の性格
第二 消費税の基本的な仕組み
1 課税対象となる取引
2 非課税となる取引
3 免税となる取引
4 非課税取引と免税取引の違い
5 不課税取引
6 納税義務者
7 免税事業者
8 課税標準
9 税率
(参考) 付加価値税率(標準税率及び食料品に対する適用税率)の国際比較
10 納付税額の計算
11 納税地
12 申告・納付
13 記帳・帳簿等の保存
14 消費者価格の表示
15 地方消費税の概要
第三 軽減税率制度の仕組み
? はじめに
1 軽減税率制度の導入趣旨
2 安定的な恒久財源の確保
3 軽減税率制度の円滑な導入・運用のための検証、取組み
4 軽減税率制度の実施に伴い必要となる事業者の基本的な対応
? 軽減税率の対象品目
1 国内取引における軽減税率の対象品目
2 輸入取引における軽減税率の対象品目
3 飲食料品等に係る軽減税率と標準税率の適用区分表
? 税額計算の方法及び特例の施行スケジュール
? 区分記載請求書等保存方式(平成31年10月1日~平成35年9月30日まで)
1 帳簿及び請求書等の記載事項及び納付税額の計算
2 売上税額の計算の特例措置
3 仕入税額の計算の特例措置
4 消費税額及び地方消費税額の計算方法
5 売上税額又は仕入税額の計算特例措置の適用関係
? 適格請求書等保存方式(平成35年10月1日以降)
1 適格請求書発行事業者の登録制度の創設
2 適格請求書発行事業者の義務等
3 仕入税額控除の要件等
4 売上税額の計算方法
5 仕入税額の計算方法
第四 軽減税率対策補助金制度の概要
大谷 信義[オオタニ ノブヨシ]
監修
吉田 一宗[ヨシダ カズムネ]
著・文・その他
内容説明
軽減税率の対象範囲について具体例を記載し、「区分記載征求書等保存方式」における消費税の税額計算の方法等について「ポイント形式」で整理!!
目次
第1 消費税の性格
第2 消費税の基本的な仕組み(課税対象となる取引;非課税となる取引;免税となる取引;非課税取引と免税取引の違い;不課税取引 ほか)
第3 軽減税率制度の仕組み(はじめに;軽減税率の対象品目;税額計算の方法及び特例の施行スケジュール;区分記載征求書等保存方式(平成31年10月1日~平成35年9月30日まで)
適格請求書等保存方式(平成35年10月1日以降))
第4 軽減税率対策補助金制度の概要
著者等紹介
吉田一宗[ヨシダカズムネ]
1952年新潟県生まれ。1971年関東信越国税局採用。1980~1984年国税庁間税部消費税課で間接税の執行事務に従事。1984~2001年大蔵省(現財務省)主税局税制第二課で間接税制の企画立案事務に従事。2001年十日町税務署長。2007年関東信越国税局人事第一課長。2011年国税庁課税総括課消費税室長。2012年熊本国税局長。2013年退官・税理士開業。2013年全国間税会総連合会専務理事に就任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- ダメ貴族になりたい公爵令嬢【タテヨミ】…