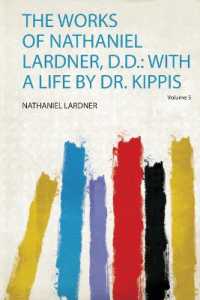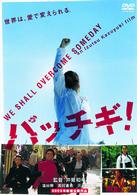出版社内容情報
心理臨床、精神科医療、精神保健福祉など、さまざまなメンタルヘルスの現場では、心理学を含め、人文・社会科学的なアプローチが中心となっている。しかし、精神疾患は脳という臓器の病気でもある。脳について、どれだけ理解した上でこうした仕事をしていけばよいのか。脳科学と臨床という両方の立場から精神疾患に取り組んできた著者が、分子や細胞からでなく、メンタルヘルス専門職が日々感じる臨床的疑問を手がかりに、知っておくべき脳科学の知識をわかりやくくまとめる。
第?部?臨床心理と脳
第1章 無意識と脳
夢と脳波/夢と機能的MRI/無意識の脳研究
第2章 認知療法と脳
情動とは何か/うつ病的認知と扁桃体/ニューロフィードバック
第3章 カウンセリングと脳
二人の機能的MRIの同時記録/瞬きの同期/脳同士の同期
第4章 認知機能検査と脳
認知機能の診方/損傷研究で注意すべき点/離断症候群/損傷研究により明らかにされた脳の高次機能
第5章 虐待と脳
動物実験/養育行動の脳科学/オスの攻撃行動/輸送反応/社会問題の解決に向けて
第?部 病気からわかる脳の働き
第6章 パーキンソン病とドーパミン
脳皮質/小脳/大脳基底核/神経伝達物質と受容体/ドーパミン受容体
第7章 依存と側坐核
側坐核とは/ドーパミンと報酬
第8章 睡眠覚醒障害とオレキシン
さまざまな睡眠覚醒障害/ナルコレプシーとは/ナルコレプシーの原因
第9章 てんかんとイオンチャネル
てんかんの生物学
第?部?精神疾患と脳
第10章 自閉スペクトラム症とシナプス
自閉症は増えているのか/診断の広がり/自閉症の原因/ゲノムとは/自閉症とゲノム/動物モデル
第11章 統合失調症と脳の同期
統合失調症とは/統合失調症の原因探求/動物モデル研究/抑制性神経細胞の機能/意識と脳波の同期
第12章 認知症の治療は可能か
アルツハイマー病の原因/創薬研究/なぜアミロイドβが蓄積するのか/凝集タンパク質の伝播/レビー小体病とαシヌクレイン
第13章 性同一性障害と脳
性同一性障害の原因
第14章 摂食障害とペプチド
グレリンとレプチン/摂食障害と脳
第15章 うつ病と神経可塑性
変貌するうつ病/さまざまなうつ病/うつ病の治療/なぜうつ病の原因が解明されてこなかったのか?/抗うつ薬の作用機序の研究/うつ病の神経可塑性仮説/うつ病とモノアミン神経核/うつ病と手綱核/うつ病と炎症/季節性うつ病
第16章 PTSDと神経新生
PTSDと動物モデル/神経新生の役割/NMDA受容体の働き
第17章 双極性障害と視床室傍核
双極性障害とリチウム/躁とうつのメカニズム/ゲノム研究/気分安定神経系はあるのか/モデルマウス/原因神経回路を求めて
加藤 忠史[カトウ タダフミ]
著・文・その他
目次
第1部 臨床心理と脳(無意識と脳;認知療法と脳;カウンセリングと脳 ほか)
第2部 病気からわかる脳の働き(パーキンソン病とドーパミン;依存と側坐核;睡眠覚醒障害とオレキシン ほか)
第3部 精神疾患と脳(自閉スペクトラム症とシナプス;統合失調症と脳の同期;認知症の治療は可能か ほか)
著者等紹介
加藤忠史[カトウタダフミ]
1963年東京都生まれ。1988年東京大学医学部卒業。1989年滋賀医科大学附属病院精神科助手。1995年~1996年文部省在外研究員としてアイオワ大学精神科にて研究。1997年東京大学医学部精神神経科助手、1999年講師。2001年理化学研究所脳科学総合研究センター精神疾患動態研究チームチームリーダー。現在、理化学研究所脳神経科学研究センター精神疾患動態研究チームチームリーダー。非常勤等:脳科学研究戦略推進プログラム・プログラムスーパーバイザー、日本うつ病センター・六番町メンタルクリニック・非常勤医師、東京大学大学院医学系研究科連携教授、広島大学客員教授、順天堂大学客員教授、藤田保健衛生大学客員教授他(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。