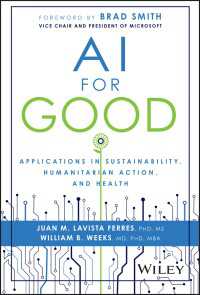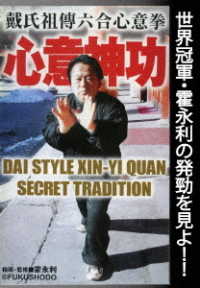目次
第1部 身体とは何か?(身体自我と物質的なものという不確かな領域;性的図式―『知覚の現象学』における転位とトランスジェンダー)
第2部 ホモエラティックス(ボーイズ・オブ・ザ・レックス―トランスジェンダーと社会構築;トランスフェミニズムとジェンダーの未来)
第3部 性的差異を超えること(性的差異のエチカをトランスする―リュス・イリガライと性的未決定性の場;性的無差異と限界の問題)
第4部 法を超えて(文字=手紙を保留すること―国有財産としてのセックス)
著者等紹介
サラモン,ゲイル[サラモン,ゲイル] [Salamon,Gayle]
カリフォルニア大学バークレー校で博士号を取得。その後、プリンストン大学の英語学の助教を経て、現在、同・大学の英語学、及び、ジェンダー&セクシュアリティ・スタディーズ・プログラムの教授
藤高和輝[フジタカカズキ]
大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。現在、大阪大学人間科学研究科助教(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヒナコ
3
トランスジェンダースタディーズについて書かれた専門書の待望の翻訳。内容は前半の理論編と後半の批評部分で構成されている。 前半部分と最終章「文字=手紙を保留すること――国有財産としてセックス」が特に面白かった。→2019/12/13
まあい
1
トランスジェンダー・スタディーズの重要著作、待望の翻訳。精神分析の「身体自我」論と、メルロ=ポンティの現象学的身体論を発展させることで、トランスジェンダーの身体経験を理論化している。また、社会構築主義に対する誤解を丁寧に解消している点も重要である。(引用)「社会的構築は身体的存在の「感じられ方(フェルト・センス)に対立するものと解釈されてはならないのだ。というのも、身体は社会的に構築されているということとその感じられ方(フェルト・センス)は否定できないということとは同時に主張可能だからである」(123頁)2019/10/14
サイトウ
0
卒論に引用
たかたか
0
社会構築主義とフェルトセンスが同時に成り立ちうることを理論的に説明している点でも重要だと感じる。当事者らしさ、男性らしさ、女性らしさなどの議論が当事者学、当事者研究と通ずる部分があり興味深かった。 訳者解説の中のポスト・トランスセクシュアルについての記述とストーンからの引用が、私の研究と通ずる部分があった。「『パスする』のではなく、むしろ積極的に『読まれる(リード)』ことであり、さらに『今まで自分について他人が書いていた言語に『自分自身を書き込んで』いこう』という戦略である。」(p.344)2020/03/15