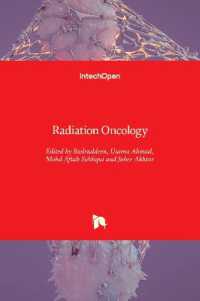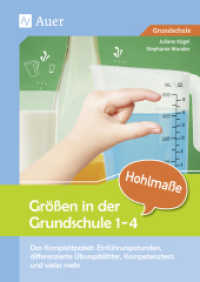内容説明
“視覚の近代”の成立に決定的な役割を果たした“観察者”の誕生。身体は、どのように社会的、リビドー的、テクノロジー的な装置の一要素に組み込まれようとしているのか?視覚文化の根本に迫る記念碑的名著。
目次
第1章 近代と観察者の問題
第2章 カメラ・オブスキュラとその主体
第3章 主観的視覚と五感の分離
第4章 観察者の技法
第5章 視覚的=幻視的抽象化(ヴィジョナリー)
著者等紹介
クレーリー,ジョナサン[クレーリー,ジョナサン][Crary,Jonathan]
米国コネティカット州ニュー・ヘイヴン生まれ。1975年コロンビア大学卒業後、1987年に同大学で博士号取得。現在、コロンビア大学教授であり、プリンストン大学建築学科客員教授も勤める。また、「ゾーン・ブックス」(1986‐92)創設時以来の基幹編集委員
遠藤知巳[エンドウトモミ]
1965年大阪府生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。日本女子大学人間社会学部助教授。専攻は近代社会論・言説分析(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲニウスロキ皇子
2
CG技術などに代表されるように視角は現実の空間から切り離され、抽象的な空間への定位が進んでいる。このような視角の抽象化はいかに進行してきたのか。この問題意識をフーコー的な歴史分析法により検証する。その際に著者は19世紀初頭とそれ以前の時代における視覚をめぐる言説の連続性ではなく断絶に、視覚の抽象化の萌芽を見出している。その分析は鮮やかで、当時の様々な学問領域を横断しながら、視覚の在り方を示す様は圧巻。でも、せっかく観察する主体の在り方を主題にしたのだから、観察される主体の在り方も気になるのが人間といふもの2011/02/10
DABAN
1
1810年から40年にかけて、視覚をめぐる人間と対象の関係は大きく再編成された。それはしばしばいわれる写真の登場、すなわち世界を固定して切り取る視点の確立などではない。世界を外部から見る視点は、むしろ18世紀のカメラ・オブスキュラと結びついている。19世紀に成立したのは、見る主体と見られる対象が一体となって動的な経験をつくりだす視覚システムだったのである。2020/02/28
まりこさん
1
帯と内容が一致していないが、系譜をたどることができた。機械仕掛の女性を一生追って行きたい私にとっては、示唆に富む一冊だけど、たぶん、内容が予想外、という人も多いんじゃないかな?2014/06/04
ぜっとん
1
本当かよと思う部分が無いでもないが、多分この本の価値はそういう部分にはない。要するに、あまりに現代的な問題でもある視覚(観察者)の問題を、19世紀における断裂(視覚の肉体化による新しいリアルと、新しい視覚の特権化)から描くわけだが、恐らく真に問題にされるべきは内容より方法と口調なのであろう。新装版あとがきで、「鮮やかさとあざとさ」と言っているのもわからないではない感覚だ。そこまで精読できたわけではないが、非常にエキサイティングな論考で楽しめた。2013/10/22
HAL9777
0
観察者に関する知の系譜を視覚装置を通じて辿る。しかし、どうしてこの知への欲求や組織編成が覇権的になったのかがわからない。また、19世紀の視覚的言説の切断は、どのように現在に接続されるのか。近代化によって合理化された運動形態に眼を適応させる過程が生じるならば、それは手、すなわち触覚にも生じることであろう。視覚の言説が身体的経験へと移行していることを見ると、余計に触覚性が際立つように感じられる。触覚性は視覚を構成するものとしてしか触れられないが、知覚の分離によって独立した触覚がいかなる意味を持つのだろうか。2025/01/03